
 東急5050系 元町•中華街-渋谷.mp3
東急東横線、みなとみらい線で録音をしました。
ー東急5050系についてー
5050系は、8000系・9000系の置き換え用として2004年に東横線向けとして登場し2016年までに8両編成が27編成(216両)、10両編成が10編成(100両)、そして田園都市線として投入される予定だった5000系8両編成が4編成(32両)、計41編成(348両)が製造されました。
JR東日本旅客鉄道と共同開発された E231系をベースに造られ、部品の共通化などをすることによってコストダウンを図られている。ホームと車両の乗降口の段差を極力なくすなどのバリアフリー対策なども重視しており、客室内のガラスにはカーテンな どの日よけが着いていない代わりに紫外線カットのガラスを採用、冷房の効率アップにもなっている。東横線5050系の特徴としては、通勤型車両としては初めてフルカラーLEDの行先表示機を採用しています。後に製造された田園都市線向けの5000系、目黒線向けの5080系にも波及されています。
車体幅の基準寸法が5000系の2770ミリメートルから2798ミリメートルに拡張して定員人数を増やすなどの改良が加えられています。
東急5050系 元町•中華街-渋谷.mp3
東急東横線、みなとみらい線で録音をしました。
ー東急5050系についてー
5050系は、8000系・9000系の置き換え用として2004年に東横線向けとして登場し2016年までに8両編成が27編成(216両)、10両編成が10編成(100両)、そして田園都市線として投入される予定だった5000系8両編成が4編成(32両)、計41編成(348両)が製造されました。
JR東日本旅客鉄道と共同開発された E231系をベースに造られ、部品の共通化などをすることによってコストダウンを図られている。ホームと車両の乗降口の段差を極力なくすなどのバリアフリー対策なども重視しており、客室内のガラスにはカーテンな どの日よけが着いていない代わりに紫外線カットのガラスを採用、冷房の効率アップにもなっている。東横線5050系の特徴としては、通勤型車両としては初めてフルカラーLEDの行先表示機を採用しています。後に製造された田園都市線向けの5000系、目黒線向けの5080系にも波及されています。
車体幅の基準寸法が5000系の2770ミリメートルから2798ミリメートルに拡張して定員人数を増やすなどの改良が加えられています。 東急2020系 押上→中央林間.m4a
東急田園都市線の新車です。東急8500系の置き換えを目的に製造されています。同時期に登場した東急大井町線の6020系と同じ設計になっている。
〜東急2020系について〜
車体
車体構造は、総合車両製作所のステンレス車体のブランドであるsustina(サスティナ)による軽量ステンレス車体としており、「Sustina S24シリーズ」の、車体長20メートルの4ドアステンレス車として製造。レーザー溶接の積極的な採用、骨組の軽量化などで、アルミ車体と同等の車体軽量化を図り、車両外観と内装でも溶接痕を減らしている。
客室扉のドア間隔はホームドアの開口範囲に合うように4820mmとしており、窓の構成は固定窓と下降窓の組み合わせとしている。客室扉の内側は、混雑時に扉が開く際に戸袋に荷物などが引き込まれるのを防止するため、素材に表面が滑りやすい素材を採用している。前部標識灯と前照灯はLED照明を使用しており、前照灯は前面下部に4灯と前面上部に2灯の計6灯としている。ロービーム時では下部の4灯を使用するが、ハイビーム時は上部の2灯を加えて6灯としており、夜間時での視認性の向上を図っている。また、先頭車の屋根上には、また、列車無線アンテナのほかに、INTEROSによる通信にも使用されるWiMAXアンテナを設置している。
内装
天井の客室灯は長い40W相当のLED照明とし、つり手棒の配置変更に合わせて配置の見直しを行い、中間車では従来の24灯から22灯とし、先頭車は従来の22灯から20灯としているが、その中に架線停電時に備えて蓄電池からの電力で点灯する予備灯を、中間車では従来の4灯から11灯とし、先頭車は従来の2灯から10灯としている。枕木方向のつり手棒は側面天井部と接続をすることにより、ロールバーの補強構造をすること構成して側面衝突に対する車両変形量の抑制を図っている。腰掛は2013年以降に導入の5000系の一部車両で採用されているハイバック仕様のロングシートを採用している。車椅子とベビーカーの乗客が利用するフリースペースは各車両の車端部に1か所ずつ設置しており、普通の乗客が利用できやすいように、側面の窓に2段の手すりと妻面に腰当を設置しており、フリースペースであることが分かるように車体外部側面と車内の床敷物に車椅子マークとベビーカーマークを大きく表示している。なお、優先席は先頭車は車端部にあるフリースペースの向かいに3席と各中間車は車端部にあるフリースペースの向かいに3席とそれとは反対側にある車端部に6席設けており、側面から座席の袖仕切を介して妻面までに黄色の帯を付けることで、一般席と区別している。妻面の引戸の戸閉装置は5000系の重力式からぜんまいの力で自動にゆっくり戻る方式に変更している。また、防犯カメラを各車に2台ずつ設置。
扉間座席中央の側窓上部と妻面引戸上部にデジタルサイネージ(電子看板)を設置している。これは21.5インチサイズの車内表示器であり、扉間座席中央の側窓上部に設置されているものは、3つ横に連続配置されており、これにより、3画面で一つの繋がった画面のように使用することができるようになっている。また、扉鴨居部には17インチの車内案内表示器が2つ横に設置されており、停車駅表示案内のほか、行先情報、ドアの開方向情報、乗り換え案内、乗車マナーなどについて表示する。
乗務員室
前面ガラスの面積を広げて視界の拡大を図っており、主幹制御器は運転台中央に配置されたワンハンドルマスコンとしており、その前方に2つのモニター装置が配置されている。モニター装置はE235系で使用されているINTEROSの導入により、モニター装置に計器・表示灯類などの情報集約を進めており、これにより計器・表示灯類などをモニター装置で表示することが可能となっている。相互乗り入れの際に各社の車両においてその機器配置が異なり、乗務員が運転の際に取扱いの負担が重いことを考慮して、東京地下鉄(東京メトロ)・東武鉄道(東武)・西武鉄道(西武)の関係者と運転台共通化の協議を行い、それに合わせて相互乗り入れする各社が保有している車両(東京メトロ13000系、東武70000系、西武40000系など)との仕様共通化を行い、その他の乗り入れ線区や本車を導入しない他の東急線の車両の仕様も参考にしている。乗務員が扱う機器ついては、設計完了後にモックアップを作成して、集められた各現業職員との間で取付け高さとボタンの形状と操作感などの検証を行ない、修正している。
主要機器
列車情報管理装置(INTEROS)
INTEROSはE235系電車にも導入されている列車情報管理装置である。データ通信速度を従来と比べて40倍も向上させて大容量のデータを扱うことが可能で、車両の各機器への伝送のほかにWiMAXによるデータ通信を利用して、車両の各種データを地上システムにリアルタイムに送信して活用することが可能。
制御装置
制御装置は、三菱電機製のフルSiC-MOSFET素子を用いた2レベル式VVVFインバータ制御装置(MAP-144-15V31A形)を採用しており、1台の制御装置で主電動機4台を制御する1C4M方式としている。高速度域まで多パルスのスイッチングを行うため、主電動機の損失を低減させて省エネルギー性能を向上させており、従来の8500系と比べて半分程度の電力で走行できるようになっている。制御装置・フィルタリアクトル・高速度遮断器は独立M方式を採用しているため、各電動車に搭載されているが、2020系の8号車のデハ2820 (M2A) と2号車のデハ2220 (M2B)、6020系の5号車のデハ6520 (M2A) と2号車のデハ6220 (M2B) は高速度遮断器を、2020系ではパンタグラフを搭載する9号車のデハ2920 (M1A) と3号車のデハ2320 (M1B) に、6020系では同じくパンタグラフを搭載する6号車のデハ6620 (M1A) と3号車のデハ6320 (M1B) に集約して、自車の分も含めて2台搭載している。
主電動機
主電動機は、東芝製のTKM-18(東芝形式SEA-446)形全密閉外扇式三相かご形誘導電動機(定格電流108A、定格周波数80Hz、定格出力140kW、定格回転数2,380rpm)を採用しており、熱交換により冷却を行う方式であるため、メンテナンス頻度の低減が図られている。
制動装置
回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ方式としており、INTEROSの編成ブレーキ力管理システムからのブレーキ指令により、編成全体で応荷重制御・電空協調制御・回生ブレーキを優先する遅れ込め制御を行うことで、省エネルギ運転と空気ブレーキの制輪子(ブレーキパッド)の摩耗量の低減が図られている。
常用ブレーキを従来の7段ステップ制御から8段ステップ制御とし、8段ステップは減速度を4.0km/h/sとすることで、回生ブレーキが安定しない時や雨天時と降雪時などで安定した制動力が得られるようにしている。また、降雪時での減速度低下時のバックアップとして非常ブレーキ時の回生補足機能を新たに追加している。この機能では、非常ブレーキ作動時には、INTEROSで減速度の演算を行い、一定の減速度低下が計測された場合には、回生ブレーキを補足で使用するものであり、降雪時でのさらなる安全性を図っている。
補助電源装置
補助電源装置はIGBT素子を使用した静止形3レベルインバータであり、出力は三相交流440V、260kVAである。整流装置は補助電源装置とは別に搭載しており、出力は直流100Vである。また各車に変圧器を搭載しており、出力は交流100Vである。
電動空気圧縮機
電動空気圧縮機は潤滑油の交換や給油が不要のオイルフリーレシプロ式圧縮機を三相かご形誘導電動機で駆動させる。潤滑油を使用しないため外部のオイル排出や元空気タンク側へのオイル流出がなく、圧縮機出口の吐出量は1750ℓ/minである。
冷房装置
冷房装置は出力58.1kW(50000kcal/h)のを屋根上に1台搭載しており、予備暖房用の6.0kWのヒータを内蔵している。また、天井部の横流ファン付近にパナソニックとJR東日本テクノロジーが共同開発した空気洗浄装置の「nanoe(ナノイー)」を設置している。東急電鉄の電車としては初めての設置。
集電装置
集電装置は5000系と同じ舟体を有したシングルアーム式だが、すり板検知装置を装備している。
戸閉装置
ラック・ピニオン式のブラシレスモーターを使用した電気式戸閉装置を採用している。戸閉状態では、常に互いの引戸が押し付け合う構造となっており、従来の電気式戸閉装置のように機械的なロックをかける必要がなく、挟まれたものを引き抜きやすい特性がある。
蓄電池
5000系と同じく焼結式のアルカリ蓄電池を採用。5000系が直流100V/60Ahと列車無線の非常電源に使用する直流24V/30Ahの2種類を搭載していたのに対し、本系列は直流100V/105Ahの1種類のみとしている。
台車
台車は5000・6000系と同じく軸箱支持装置が軸梁式のボルスタレス台車空気ばね台車のTS-1041動力台車、TS-1042・TS-1042A付随台車を採用だが、台車の牽引力を車体に伝達するけん引装置はZリンク式から一本リンク式に変更されている。基礎ブレーキ装置は、踏面片押し式のユニットブレーキで、付随台車はディスクブレーキが追加されている。なおこのディスクブレーキのライニングは脱着性向上を図るため、UIC(国際鉄道連合)規格に基づいた構造としている。
駆動装置は5000・6000系と同じく中実軸平行カルダン式だが、電動機の電機子軸と輪軸の歯車駆動軸との間の継手を、CFRP製のたわみ板を使用したTD継手式から、歯車形たわみ軸継手を使用したWN継手式に変更されており、低騒音化を図っている。
東急2020系 押上→中央林間.m4a
東急田園都市線の新車です。東急8500系の置き換えを目的に製造されています。同時期に登場した東急大井町線の6020系と同じ設計になっている。
〜東急2020系について〜
車体
車体構造は、総合車両製作所のステンレス車体のブランドであるsustina(サスティナ)による軽量ステンレス車体としており、「Sustina S24シリーズ」の、車体長20メートルの4ドアステンレス車として製造。レーザー溶接の積極的な採用、骨組の軽量化などで、アルミ車体と同等の車体軽量化を図り、車両外観と内装でも溶接痕を減らしている。
客室扉のドア間隔はホームドアの開口範囲に合うように4820mmとしており、窓の構成は固定窓と下降窓の組み合わせとしている。客室扉の内側は、混雑時に扉が開く際に戸袋に荷物などが引き込まれるのを防止するため、素材に表面が滑りやすい素材を採用している。前部標識灯と前照灯はLED照明を使用しており、前照灯は前面下部に4灯と前面上部に2灯の計6灯としている。ロービーム時では下部の4灯を使用するが、ハイビーム時は上部の2灯を加えて6灯としており、夜間時での視認性の向上を図っている。また、先頭車の屋根上には、また、列車無線アンテナのほかに、INTEROSによる通信にも使用されるWiMAXアンテナを設置している。
内装
天井の客室灯は長い40W相当のLED照明とし、つり手棒の配置変更に合わせて配置の見直しを行い、中間車では従来の24灯から22灯とし、先頭車は従来の22灯から20灯としているが、その中に架線停電時に備えて蓄電池からの電力で点灯する予備灯を、中間車では従来の4灯から11灯とし、先頭車は従来の2灯から10灯としている。枕木方向のつり手棒は側面天井部と接続をすることにより、ロールバーの補強構造をすること構成して側面衝突に対する車両変形量の抑制を図っている。腰掛は2013年以降に導入の5000系の一部車両で採用されているハイバック仕様のロングシートを採用している。車椅子とベビーカーの乗客が利用するフリースペースは各車両の車端部に1か所ずつ設置しており、普通の乗客が利用できやすいように、側面の窓に2段の手すりと妻面に腰当を設置しており、フリースペースであることが分かるように車体外部側面と車内の床敷物に車椅子マークとベビーカーマークを大きく表示している。なお、優先席は先頭車は車端部にあるフリースペースの向かいに3席と各中間車は車端部にあるフリースペースの向かいに3席とそれとは反対側にある車端部に6席設けており、側面から座席の袖仕切を介して妻面までに黄色の帯を付けることで、一般席と区別している。妻面の引戸の戸閉装置は5000系の重力式からぜんまいの力で自動にゆっくり戻る方式に変更している。また、防犯カメラを各車に2台ずつ設置。
扉間座席中央の側窓上部と妻面引戸上部にデジタルサイネージ(電子看板)を設置している。これは21.5インチサイズの車内表示器であり、扉間座席中央の側窓上部に設置されているものは、3つ横に連続配置されており、これにより、3画面で一つの繋がった画面のように使用することができるようになっている。また、扉鴨居部には17インチの車内案内表示器が2つ横に設置されており、停車駅表示案内のほか、行先情報、ドアの開方向情報、乗り換え案内、乗車マナーなどについて表示する。
乗務員室
前面ガラスの面積を広げて視界の拡大を図っており、主幹制御器は運転台中央に配置されたワンハンドルマスコンとしており、その前方に2つのモニター装置が配置されている。モニター装置はE235系で使用されているINTEROSの導入により、モニター装置に計器・表示灯類などの情報集約を進めており、これにより計器・表示灯類などをモニター装置で表示することが可能となっている。相互乗り入れの際に各社の車両においてその機器配置が異なり、乗務員が運転の際に取扱いの負担が重いことを考慮して、東京地下鉄(東京メトロ)・東武鉄道(東武)・西武鉄道(西武)の関係者と運転台共通化の協議を行い、それに合わせて相互乗り入れする各社が保有している車両(東京メトロ13000系、東武70000系、西武40000系など)との仕様共通化を行い、その他の乗り入れ線区や本車を導入しない他の東急線の車両の仕様も参考にしている。乗務員が扱う機器ついては、設計完了後にモックアップを作成して、集められた各現業職員との間で取付け高さとボタンの形状と操作感などの検証を行ない、修正している。
主要機器
列車情報管理装置(INTEROS)
INTEROSはE235系電車にも導入されている列車情報管理装置である。データ通信速度を従来と比べて40倍も向上させて大容量のデータを扱うことが可能で、車両の各機器への伝送のほかにWiMAXによるデータ通信を利用して、車両の各種データを地上システムにリアルタイムに送信して活用することが可能。
制御装置
制御装置は、三菱電機製のフルSiC-MOSFET素子を用いた2レベル式VVVFインバータ制御装置(MAP-144-15V31A形)を採用しており、1台の制御装置で主電動機4台を制御する1C4M方式としている。高速度域まで多パルスのスイッチングを行うため、主電動機の損失を低減させて省エネルギー性能を向上させており、従来の8500系と比べて半分程度の電力で走行できるようになっている。制御装置・フィルタリアクトル・高速度遮断器は独立M方式を採用しているため、各電動車に搭載されているが、2020系の8号車のデハ2820 (M2A) と2号車のデハ2220 (M2B)、6020系の5号車のデハ6520 (M2A) と2号車のデハ6220 (M2B) は高速度遮断器を、2020系ではパンタグラフを搭載する9号車のデハ2920 (M1A) と3号車のデハ2320 (M1B) に、6020系では同じくパンタグラフを搭載する6号車のデハ6620 (M1A) と3号車のデハ6320 (M1B) に集約して、自車の分も含めて2台搭載している。
主電動機
主電動機は、東芝製のTKM-18(東芝形式SEA-446)形全密閉外扇式三相かご形誘導電動機(定格電流108A、定格周波数80Hz、定格出力140kW、定格回転数2,380rpm)を採用しており、熱交換により冷却を行う方式であるため、メンテナンス頻度の低減が図られている。
制動装置
回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ方式としており、INTEROSの編成ブレーキ力管理システムからのブレーキ指令により、編成全体で応荷重制御・電空協調制御・回生ブレーキを優先する遅れ込め制御を行うことで、省エネルギ運転と空気ブレーキの制輪子(ブレーキパッド)の摩耗量の低減が図られている。
常用ブレーキを従来の7段ステップ制御から8段ステップ制御とし、8段ステップは減速度を4.0km/h/sとすることで、回生ブレーキが安定しない時や雨天時と降雪時などで安定した制動力が得られるようにしている。また、降雪時での減速度低下時のバックアップとして非常ブレーキ時の回生補足機能を新たに追加している。この機能では、非常ブレーキ作動時には、INTEROSで減速度の演算を行い、一定の減速度低下が計測された場合には、回生ブレーキを補足で使用するものであり、降雪時でのさらなる安全性を図っている。
補助電源装置
補助電源装置はIGBT素子を使用した静止形3レベルインバータであり、出力は三相交流440V、260kVAである。整流装置は補助電源装置とは別に搭載しており、出力は直流100Vである。また各車に変圧器を搭載しており、出力は交流100Vである。
電動空気圧縮機
電動空気圧縮機は潤滑油の交換や給油が不要のオイルフリーレシプロ式圧縮機を三相かご形誘導電動機で駆動させる。潤滑油を使用しないため外部のオイル排出や元空気タンク側へのオイル流出がなく、圧縮機出口の吐出量は1750ℓ/minである。
冷房装置
冷房装置は出力58.1kW(50000kcal/h)のを屋根上に1台搭載しており、予備暖房用の6.0kWのヒータを内蔵している。また、天井部の横流ファン付近にパナソニックとJR東日本テクノロジーが共同開発した空気洗浄装置の「nanoe(ナノイー)」を設置している。東急電鉄の電車としては初めての設置。
集電装置
集電装置は5000系と同じ舟体を有したシングルアーム式だが、すり板検知装置を装備している。
戸閉装置
ラック・ピニオン式のブラシレスモーターを使用した電気式戸閉装置を採用している。戸閉状態では、常に互いの引戸が押し付け合う構造となっており、従来の電気式戸閉装置のように機械的なロックをかける必要がなく、挟まれたものを引き抜きやすい特性がある。
蓄電池
5000系と同じく焼結式のアルカリ蓄電池を採用。5000系が直流100V/60Ahと列車無線の非常電源に使用する直流24V/30Ahの2種類を搭載していたのに対し、本系列は直流100V/105Ahの1種類のみとしている。
台車
台車は5000・6000系と同じく軸箱支持装置が軸梁式のボルスタレス台車空気ばね台車のTS-1041動力台車、TS-1042・TS-1042A付随台車を採用だが、台車の牽引力を車体に伝達するけん引装置はZリンク式から一本リンク式に変更されている。基礎ブレーキ装置は、踏面片押し式のユニットブレーキで、付随台車はディスクブレーキが追加されている。なおこのディスクブレーキのライニングは脱着性向上を図るため、UIC(国際鉄道連合)規格に基づいた構造としている。
駆動装置は5000・6000系と同じく中実軸平行カルダン式だが、電動機の電機子軸と輪軸の歯車駆動軸との間の継手を、CFRP製のたわみ板を使用したTD継手式から、歯車形たわみ軸継手を使用したWN継手式に変更されており、低騒音化を図っている。 東急7700系(7001F)蒲田→五反田.mp3
〜東急7700系について〜
外観
7000系の時と比較してあまり変化はありませんが、雨樋が新たに設けられています。また、屋根上に新たに設置された冷房装置は東急9000系のものと同一ですが、そのカバーは営団地下鉄(現在の東京メトロ)日比谷線の車両限界に対応するために、側面を斜めに削った形状となっています。
車内
車内は東急9000系に準じた仕様に更新されています。座席は7000系の時と同じロングシートですが、定員着席を促すため、9人掛けの座席を3人ずつで区切るための仕切り板が入れられたほか、オレンジとブラウンで1スペースごとに色分けがされました。7000系のときから設置されていた車内の扇風機は、補助送風機としてそのまま残っています。
乗務員室の運転台は一新され、マスコンがワンハンドル式となっている。
集電装置 菱形パンタグラフ PT-43/PT-44/PT-44S-C
台車 軸箱守式軸箱支持空気バネ台車 TS-832(電動車) TS-835(付属車)
駆動装置 中空軸平行カルダンタワミ板継手式
主電動機 TKM-86 かご形三相誘導電動機170kW
制御装置 GTO-VVVFインバータ制御
制動装置 全電気指令式電磁直通空気ブレーキ(回生ブレーキ付)
保安装置 ATS、TASC
東急7700系(7001F)蒲田→五反田.mp3
〜東急7700系について〜
外観
7000系の時と比較してあまり変化はありませんが、雨樋が新たに設けられています。また、屋根上に新たに設置された冷房装置は東急9000系のものと同一ですが、そのカバーは営団地下鉄(現在の東京メトロ)日比谷線の車両限界に対応するために、側面を斜めに削った形状となっています。
車内
車内は東急9000系に準じた仕様に更新されています。座席は7000系の時と同じロングシートですが、定員着席を促すため、9人掛けの座席を3人ずつで区切るための仕切り板が入れられたほか、オレンジとブラウンで1スペースごとに色分けがされました。7000系のときから設置されていた車内の扇風機は、補助送風機としてそのまま残っています。
乗務員室の運転台は一新され、マスコンがワンハンドル式となっている。
集電装置 菱形パンタグラフ PT-43/PT-44/PT-44S-C
台車 軸箱守式軸箱支持空気バネ台車 TS-832(電動車) TS-835(付属車)
駆動装置 中空軸平行カルダンタワミ板継手式
主電動機 TKM-86 かご形三相誘導電動機170kW
制御装置 GTO-VVVFインバータ制御
制動装置 全電気指令式電磁直通空気ブレーキ(回生ブレーキ付)
保安装置 ATS、TASC
 京王7000系(ワンマン車) 高幡不動〜多摩動物公園.MP3
-京王7000系 4両編成-
外観
20 m両開き4扉、窓間に戸袋窓2枚、1枚下降窓2枚を、車端部に戸袋窓と1枚下降窓各1枚を備える基本配置、基本寸法は6000系と同様だが、窓がサッシレスになるとともに隅に丸みを設け、やさしさを出している。ステンレス車で戸袋窓を備えるのは珍しく、7000系登場当時の紹介記事には「20 mの軽量ステンレス車では全国初」と記載されている。幕板部中央には 車側灯を挟んで種別表示装置と行先表示装置が配置されている。
先頭車正面形状は6000系に類似し、中央に貫通扉が設置され、前面窓上に行先表示装置、種別表示装置、車号板、標識灯がある。窓サイズが左右同一となり、6000系運転室窓より下方に100 mm拡大。正面角部には銀色に塗装されたFRP製カバーが取り付けられている。
車内
バケットシート、袖仕切りの大型化、座席部へのつかみ棒の設置が行われている。UVカットガラスの採用により、巻き上げカーテンが廃止されている。
主制御装置など
主制御装置をIGBT素子のVVVFインバータ制御。主制御装置、主電動機は9000系用を基本としたものとされ、電動車はVFI-HR-2815C形主制御装置がデハ7000形に搭載。主電動機は出力150 kWのかご形三相誘導電動機HS-33535-01RBが採用されている。
台車
台車も6000系用を基本とする、車体直結式空気ばね式の東急車輛製造(以下、東急)製TS-823動力台車、TS-824付随台車を採用。台車枠がプレス構造とされ、TS-823の軸距は2,200 mm、TS-824は2,100 mmである。全台車両抱式の踏面ブレーキを装備する。サハ7550形はTS-823を装備している。
集電装置
東洋製PT-4201、ブロイメットすり板装備品がデハ7000形とデハ7400形の全車に搭載された。
補助電源装置
静止形インバータ(SIV、AC200 V、出力150 kVA)が採用され、4両編成ではデハ7050形に各1台搭載されている。
空気圧縮機
毎分吐出容量2130リットルのHB-2000形および性能は同一で小型低騒音のHS-20Dが4両編成ではクハ7700形とデハ7050形に搭載された。
冷房装置
屋上集中式46.5 kW (40,000 kcal/h) の冷房装置が各車に1台搭載された。
京王7000系(ワンマン車) 高幡不動〜多摩動物公園.MP3
-京王7000系 4両編成-
外観
20 m両開き4扉、窓間に戸袋窓2枚、1枚下降窓2枚を、車端部に戸袋窓と1枚下降窓各1枚を備える基本配置、基本寸法は6000系と同様だが、窓がサッシレスになるとともに隅に丸みを設け、やさしさを出している。ステンレス車で戸袋窓を備えるのは珍しく、7000系登場当時の紹介記事には「20 mの軽量ステンレス車では全国初」と記載されている。幕板部中央には 車側灯を挟んで種別表示装置と行先表示装置が配置されている。
先頭車正面形状は6000系に類似し、中央に貫通扉が設置され、前面窓上に行先表示装置、種別表示装置、車号板、標識灯がある。窓サイズが左右同一となり、6000系運転室窓より下方に100 mm拡大。正面角部には銀色に塗装されたFRP製カバーが取り付けられている。
車内
バケットシート、袖仕切りの大型化、座席部へのつかみ棒の設置が行われている。UVカットガラスの採用により、巻き上げカーテンが廃止されている。
主制御装置など
主制御装置をIGBT素子のVVVFインバータ制御。主制御装置、主電動機は9000系用を基本としたものとされ、電動車はVFI-HR-2815C形主制御装置がデハ7000形に搭載。主電動機は出力150 kWのかご形三相誘導電動機HS-33535-01RBが採用されている。
台車
台車も6000系用を基本とする、車体直結式空気ばね式の東急車輛製造(以下、東急)製TS-823動力台車、TS-824付随台車を採用。台車枠がプレス構造とされ、TS-823の軸距は2,200 mm、TS-824は2,100 mmである。全台車両抱式の踏面ブレーキを装備する。サハ7550形はTS-823を装備している。
集電装置
東洋製PT-4201、ブロイメットすり板装備品がデハ7000形とデハ7400形の全車に搭載された。
補助電源装置
静止形インバータ(SIV、AC200 V、出力150 kVA)が採用され、4両編成ではデハ7050形に各1台搭載されている。
空気圧縮機
毎分吐出容量2130リットルのHB-2000形および性能は同一で小型低騒音のHS-20Dが4両編成ではクハ7700形とデハ7050形に搭載された。
冷房装置
屋上集中式46.5 kW (40,000 kcal/h) の冷房装置が各車に1台搭載された。
 京王9000系 高尾山口〜つつじヶ丘.m4a
快速つつじヶ丘行を録音。快速つつじヶ丘行は調布→つつじヶ丘の区間以外は各駅に停車をします。終点のつつじヶ丘で各駅停車の新宿行に接続。
〜京王9000系〜
外観
7000系・8000系に続いてステンレス車体、20 m両開き4扉、扉間に窓2枚の基本レイアウトが採用された。ビードがなく、側扉部に縦線が見える日本車輌製造(以下、日車)標準構造が採用され、車体強度向上、軽量化のため戸袋窓を廃止。側窓は8000系と同様2枚をひと組にしたサッシュレスの1枚下降窓となったが、軽量化のため一部窓が固定式とされた。新宿線乗り入れのため、地下鉄乗り入れ車両の構造規定に従い、前面は貫通構造とされ、幅610 mmの開き戸が中央に設けられた。初代5000系のイメージを残した形状となり、傾斜をつけた側面まで回り込む曲面ガラスを採用。前面は一見平面的に見えるが、上面からみたときに半径10,000 mmの曲面で構成されており、工作の容易化のため乗務員扉部分までの前頭部がアイボリー塗装の普通鋼製とされ、スカートも同色に塗装された。正側面腰部にはイメージカラーである京王レッドと京王ブルーの帯が巻かれた。8000系で窓上に貼られていた京王レッドの帯は9000系では採用されていない。8両編成では車体下部に傾斜が設けられていたが、10両編成では直線状とされているほか、客用ドア窓支持方式も両者で異なる。車椅子スペースに隣接するドアには車椅子での乗降を考慮した傾斜が設けられた。8両編成の両車端には固定式の妻窓が設けられたが、10両編成では廃止されている。8000系に続いて車外スピーカーが設置された。
内装
車端部4人掛け、扉間7人掛けの京王線用20 m車としては標準的な配置が採用されたが、1人当たり座席寸法は8000系よりも10 mm拡大された450 mmとなっている。座席は片持ち式のバケット式が採用され、色は8000系よりやや濃いめのローズピンクとなった。7人掛け部分には3人と4人に仕切る握り棒が設けられているほか、一部の座席の裏には非常脱出時に用いる階段が取り付けられている。出入口脇には袖仕切り板を設け、立客の背もたれと座客の保護の機能を持たせているが、8両編成と10両編成では袖仕切りの形状が異なり、10両編成のうち9736編成以降の15本では握り棒が緩やかな曲線状に変更されている。明るさと清楚さを出すため壁と天井は白色系とされた。妻部は乗務員室後部を含み8両編成ではグレーの木目模様だが、10両編成では他の壁と同色とされた。床は茶系のツートンカラーで、中央部が薄く、座席付近が濃くなっている。天井は冷房ダクトと横流ファンを埋め込んだ平天井で、8000系よりも天井高さが25 mm高い2,270 mmとなった。8両編成の天井はFRP製だが、10両編成では新火災対策基準対応のため塗装アルミ材が採用されている。8両編成では2・4・6両目の京王八王子寄りに貫通路を仕切る引き戸が設けられているが、10両編成では京王八王子寄り先頭車を除くすべての車両への設置に変更。バリアフリー対応として、8両編成の2両目と7両目、10両編成の2・4・6・9両目の車端部1箇所に車椅子スペースが設けられた。車端4人がけ部のつり手・荷棚・座席をそれぞれ50 mm・100 mm・10 mm低くしている。車椅子スペースに隣接するドアの靴擦り部には傾斜が設けられ、車椅子での乗降容易化が図られている。京王で初めてドアチャイムと旅客案内装置が設けられ、8両編成全編成と2006年製までの10両編成5本にはLED式旅客案内装置が客用ドア上に1両に4箇所設置されたが、2007年以降製造の10両編成15本はLCD式車内案内表示器がすべての客用ドアの上に設けられている。
乗務員室
運転席からの視認性向上のため京王で初めて高乗務員室が採用され、従来車より乗務員室位置が約200 mm高くなっている。乗務員室はグレー系に塗装され、8000系のデジタル式速度計に変えて7000系以前と同様機械式の速度計が採用された。従来車同様ワンハンドルマスコンが採用されたが、ハンドル本体は8000系よりも大型化されている。力行2段目で定速制御が行うことができる。乗務員の支援、行先・種別表示、検修時の支援などを目的としたモニタ装置が乗務員室上部に設置された。8両編成の京王八王子寄り先頭車は2両編成を連結して幌で貫通することが想定されていたため可動式の仕切りが設置されているが、その他の先頭車には仕切りがない。8両編成には6000系・7000系と併結するための伝送変換器が設けられた。 10両編成には新宿線用ATCが設置され、一部の10両編成は京王ATCが設置された。京王ATCは後に全車に設置されている。
主要機器
主制御装置、主電動機
定格3,300 V・1,200 AのIGBTを用いたVVVFインバータ制御が採用され、1つの主制御装置で電動車2両1ユニット、8個の主電動機を制御するが、4個ずつ解放可能な2群構成とされた。日立製作所(以下、日立)製[2]VFI-HR-2820が採用され、デハ9000形に搭載。10両編成の9100番台はユニットを組まない単独M車として使用されるため、1群のみ搭載のVFI-HR-1420が搭載されている。京王線用車両として初めてIGBT素子を使用した制御装置を採用した。
主電動機は従来車より高出力の出力170 kW(定格電圧1,100 V、電流115 A)のかご形三相誘導電動機、日立製HS-33534-02RBおよび日立製EFK-K60が採用された。
駆動装置は京王従来車と同様WN駆動方式が採用され、歯車比は85:14である。
制動装置
制動装置は電気指令式 ナブコ製HRDA-1が8000系に続いて採用された。電動車と非電動車各1両を1組として回生ブレーキを優先する制御が採用された。9000系では全車両にブレーキコントロールユニットが搭載され、車両ごとに独立してブレーキ信号を受信している。踏面ブレーキは8000系最終製造車と同じユニット式の型押しブレーキが採用されている。
台車
8000系最終製造車と同一の東急車輛製造(以下、東急)製[2]軸梁式軸箱支持ボルスタレス空気ばねのTS-1017動力台車、TS-1018付随台車(いずれも固定軸距2,200 mm、車輪経860 mm)が採用された。台車枠の横梁は空気ばねの補助空気室を兼ねている。
集電装置
東洋電機製造製PT-7110シングルアームパンタグラフがデハ9000形全車と、8両編成の9100番台を除くデハ9050形に搭載された。
補助電源装置
8両編成のうち9706編成までの8本は出力170 kVAの静止形インバータ (SIV)が、9707編成・9708編成は空調装置能力増強のため210 kVAのSIV[2]が、10両編成には出力250 kVAのSIVがそれぞれデハ9050形に搭載された。
空気圧縮機
毎分吐出容量1,600リットルのスクリュー式電動空気圧縮機クノールブレムゼ製[注釈 10]SL-22がデハ9050形に搭載された。
冷房装置
9706編成までの8両編成には屋上集中式48.84 kW (42,000 kcal/h) の冷房装置が各車に1台、9707編成・9708編成と10両編成には屋上集中式58.14 kW (50,000 kcal/h) のものが同様に各車に1台搭載された。
京王9000系 高尾山口〜つつじヶ丘.m4a
快速つつじヶ丘行を録音。快速つつじヶ丘行は調布→つつじヶ丘の区間以外は各駅に停車をします。終点のつつじヶ丘で各駅停車の新宿行に接続。
〜京王9000系〜
外観
7000系・8000系に続いてステンレス車体、20 m両開き4扉、扉間に窓2枚の基本レイアウトが採用された。ビードがなく、側扉部に縦線が見える日本車輌製造(以下、日車)標準構造が採用され、車体強度向上、軽量化のため戸袋窓を廃止。側窓は8000系と同様2枚をひと組にしたサッシュレスの1枚下降窓となったが、軽量化のため一部窓が固定式とされた。新宿線乗り入れのため、地下鉄乗り入れ車両の構造規定に従い、前面は貫通構造とされ、幅610 mmの開き戸が中央に設けられた。初代5000系のイメージを残した形状となり、傾斜をつけた側面まで回り込む曲面ガラスを採用。前面は一見平面的に見えるが、上面からみたときに半径10,000 mmの曲面で構成されており、工作の容易化のため乗務員扉部分までの前頭部がアイボリー塗装の普通鋼製とされ、スカートも同色に塗装された。正側面腰部にはイメージカラーである京王レッドと京王ブルーの帯が巻かれた。8000系で窓上に貼られていた京王レッドの帯は9000系では採用されていない。8両編成では車体下部に傾斜が設けられていたが、10両編成では直線状とされているほか、客用ドア窓支持方式も両者で異なる。車椅子スペースに隣接するドアには車椅子での乗降を考慮した傾斜が設けられた。8両編成の両車端には固定式の妻窓が設けられたが、10両編成では廃止されている。8000系に続いて車外スピーカーが設置された。
内装
車端部4人掛け、扉間7人掛けの京王線用20 m車としては標準的な配置が採用されたが、1人当たり座席寸法は8000系よりも10 mm拡大された450 mmとなっている。座席は片持ち式のバケット式が採用され、色は8000系よりやや濃いめのローズピンクとなった。7人掛け部分には3人と4人に仕切る握り棒が設けられているほか、一部の座席の裏には非常脱出時に用いる階段が取り付けられている。出入口脇には袖仕切り板を設け、立客の背もたれと座客の保護の機能を持たせているが、8両編成と10両編成では袖仕切りの形状が異なり、10両編成のうち9736編成以降の15本では握り棒が緩やかな曲線状に変更されている。明るさと清楚さを出すため壁と天井は白色系とされた。妻部は乗務員室後部を含み8両編成ではグレーの木目模様だが、10両編成では他の壁と同色とされた。床は茶系のツートンカラーで、中央部が薄く、座席付近が濃くなっている。天井は冷房ダクトと横流ファンを埋め込んだ平天井で、8000系よりも天井高さが25 mm高い2,270 mmとなった。8両編成の天井はFRP製だが、10両編成では新火災対策基準対応のため塗装アルミ材が採用されている。8両編成では2・4・6両目の京王八王子寄りに貫通路を仕切る引き戸が設けられているが、10両編成では京王八王子寄り先頭車を除くすべての車両への設置に変更。バリアフリー対応として、8両編成の2両目と7両目、10両編成の2・4・6・9両目の車端部1箇所に車椅子スペースが設けられた。車端4人がけ部のつり手・荷棚・座席をそれぞれ50 mm・100 mm・10 mm低くしている。車椅子スペースに隣接するドアの靴擦り部には傾斜が設けられ、車椅子での乗降容易化が図られている。京王で初めてドアチャイムと旅客案内装置が設けられ、8両編成全編成と2006年製までの10両編成5本にはLED式旅客案内装置が客用ドア上に1両に4箇所設置されたが、2007年以降製造の10両編成15本はLCD式車内案内表示器がすべての客用ドアの上に設けられている。
乗務員室
運転席からの視認性向上のため京王で初めて高乗務員室が採用され、従来車より乗務員室位置が約200 mm高くなっている。乗務員室はグレー系に塗装され、8000系のデジタル式速度計に変えて7000系以前と同様機械式の速度計が採用された。従来車同様ワンハンドルマスコンが採用されたが、ハンドル本体は8000系よりも大型化されている。力行2段目で定速制御が行うことができる。乗務員の支援、行先・種別表示、検修時の支援などを目的としたモニタ装置が乗務員室上部に設置された。8両編成の京王八王子寄り先頭車は2両編成を連結して幌で貫通することが想定されていたため可動式の仕切りが設置されているが、その他の先頭車には仕切りがない。8両編成には6000系・7000系と併結するための伝送変換器が設けられた。 10両編成には新宿線用ATCが設置され、一部の10両編成は京王ATCが設置された。京王ATCは後に全車に設置されている。
主要機器
主制御装置、主電動機
定格3,300 V・1,200 AのIGBTを用いたVVVFインバータ制御が採用され、1つの主制御装置で電動車2両1ユニット、8個の主電動機を制御するが、4個ずつ解放可能な2群構成とされた。日立製作所(以下、日立)製[2]VFI-HR-2820が採用され、デハ9000形に搭載。10両編成の9100番台はユニットを組まない単独M車として使用されるため、1群のみ搭載のVFI-HR-1420が搭載されている。京王線用車両として初めてIGBT素子を使用した制御装置を採用した。
主電動機は従来車より高出力の出力170 kW(定格電圧1,100 V、電流115 A)のかご形三相誘導電動機、日立製HS-33534-02RBおよび日立製EFK-K60が採用された。
駆動装置は京王従来車と同様WN駆動方式が採用され、歯車比は85:14である。
制動装置
制動装置は電気指令式 ナブコ製HRDA-1が8000系に続いて採用された。電動車と非電動車各1両を1組として回生ブレーキを優先する制御が採用された。9000系では全車両にブレーキコントロールユニットが搭載され、車両ごとに独立してブレーキ信号を受信している。踏面ブレーキは8000系最終製造車と同じユニット式の型押しブレーキが採用されている。
台車
8000系最終製造車と同一の東急車輛製造(以下、東急)製[2]軸梁式軸箱支持ボルスタレス空気ばねのTS-1017動力台車、TS-1018付随台車(いずれも固定軸距2,200 mm、車輪経860 mm)が採用された。台車枠の横梁は空気ばねの補助空気室を兼ねている。
集電装置
東洋電機製造製PT-7110シングルアームパンタグラフがデハ9000形全車と、8両編成の9100番台を除くデハ9050形に搭載された。
補助電源装置
8両編成のうち9706編成までの8本は出力170 kVAの静止形インバータ (SIV)が、9707編成・9708編成は空調装置能力増強のため210 kVAのSIV[2]が、10両編成には出力250 kVAのSIVがそれぞれデハ9050形に搭載された。
空気圧縮機
毎分吐出容量1,600リットルのスクリュー式電動空気圧縮機クノールブレムゼ製[注釈 10]SL-22がデハ9050形に搭載された。
冷房装置
9706編成までの8両編成には屋上集中式48.84 kW (42,000 kcal/h) の冷房装置が各車に1台、9707編成・9708編成と10両編成には屋上集中式58.14 kW (50,000 kcal/h) のものが同様に各車に1台搭載された。 京王1000系(初期車) 渋谷〜吉祥寺.m4a
急行運用を録音しました。
〜京王1000系について〜
外観
3000系に引き続いてステンレス製であるが、輸送力増強を目的として、各車両の全長は同系列の18m級から井の頭線用車両では初の20m級となり、客用扉の数も同系列の片側3箇所から4箇所となった。乗車定員も増え、車内の天井も約10センチ高くなった。同系列と同様に裾絞りがあり、外板は4次車・1715Fまではビード(凹凸)付きである。加えて車体側面に車外放送スピーカーも設置された。行先表示器はLED式でローマ字を併記するが、1710Fまでは当初はローマ字と各停運用時の種別表記がなかった。書体はゴシック体である。
先頭形状は3000系更新車と共通イメージであるが、新たに非常用貫通扉を設置し、これを助士席側に寄せた構造となっている。この部分の塗装は編成ごとにパステルカラー7色(レインボーカラー)を使い分けている。
貫通扉下部には車両番号が表記され、その周囲にヘッドマークを装着するステーが設けられている。
乗務員室
井の頭線車両で初のワンハンドル式主幹制御器。また、京王の車両では初の電子警笛を装備。
主要機器
主制御装置、主電動機
本系列は井の頭線初のVVVFインバータ制御車両。
VVVFインバータ制御装置の制御素子は1710Fまでの奇数編成が東洋電機製造製GTOサイリスタ (RG655-A-M 4500V/3000A)、偶数編成は日立製作所製IGBT (VFI-HR2480A 2000V/325A) で、各M車に搭載される。1711F - 15Fは東洋電機製造製IGBTで、デハ1000形にはユニットを組むデハ1050形も制御するATR-H8180-RG682A-Mを、単独M車のデハ1100形はATR-H4180-RG683A-Mを搭載する。1721F以降では日立製作所製のIGBTで、デハ1000形にVFI-HR2820Kを、デハ1100形にVFI-HR1420Tを搭載する。
朝ラッシュ時の使用を想定した定速制御の機能を持っているが、井の頭線内では頻繁に加減速を行っているため、使用する機会は少ない。
屋上機器
パンタグラフは全編成とも3基搭載である。屋根上に設置された冷房装置は集中式で、補助送風機としてラインデリアを装備する。ベンチレーターは設置されていない。
京王1000系(初期車) 渋谷〜吉祥寺.m4a
急行運用を録音しました。
〜京王1000系について〜
外観
3000系に引き続いてステンレス製であるが、輸送力増強を目的として、各車両の全長は同系列の18m級から井の頭線用車両では初の20m級となり、客用扉の数も同系列の片側3箇所から4箇所となった。乗車定員も増え、車内の天井も約10センチ高くなった。同系列と同様に裾絞りがあり、外板は4次車・1715Fまではビード(凹凸)付きである。加えて車体側面に車外放送スピーカーも設置された。行先表示器はLED式でローマ字を併記するが、1710Fまでは当初はローマ字と各停運用時の種別表記がなかった。書体はゴシック体である。
先頭形状は3000系更新車と共通イメージであるが、新たに非常用貫通扉を設置し、これを助士席側に寄せた構造となっている。この部分の塗装は編成ごとにパステルカラー7色(レインボーカラー)を使い分けている。
貫通扉下部には車両番号が表記され、その周囲にヘッドマークを装着するステーが設けられている。
乗務員室
井の頭線車両で初のワンハンドル式主幹制御器。また、京王の車両では初の電子警笛を装備。
主要機器
主制御装置、主電動機
本系列は井の頭線初のVVVFインバータ制御車両。
VVVFインバータ制御装置の制御素子は1710Fまでの奇数編成が東洋電機製造製GTOサイリスタ (RG655-A-M 4500V/3000A)、偶数編成は日立製作所製IGBT (VFI-HR2480A 2000V/325A) で、各M車に搭載される。1711F - 15Fは東洋電機製造製IGBTで、デハ1000形にはユニットを組むデハ1050形も制御するATR-H8180-RG682A-Mを、単独M車のデハ1100形はATR-H4180-RG683A-Mを搭載する。1721F以降では日立製作所製のIGBTで、デハ1000形にVFI-HR2820Kを、デハ1100形にVFI-HR1420Tを搭載する。
朝ラッシュ時の使用を想定した定速制御の機能を持っているが、井の頭線内では頻繁に加減速を行っているため、使用する機会は少ない。
屋上機器
パンタグラフは全編成とも3基搭載である。屋根上に設置された冷房装置は集中式で、補助送風機としてラインデリアを装備する。ベンチレーターは設置されていない。 京王5000系 本八幡〜橋本.m4a
日中に運転が行われている都営新宿線 本八幡〜京王相模原線 橋本の運用を録音しました。都営新宿線は各停で京王線は区間急行となる。
〜京王5000系〜
外観
従来車両よりシャープで立体的な前面形状が採用されており、京王の車両としては初めて前面が大きく傾斜している。前面はスマートな列車を表現するためカラーリングに黒が多用され、窓上部に京王レッドの、窓下部に京王ブルーの帯が巻かれており、包容感を感じさせる温かみの中に気品のある表情を持たせ、コーポレートカラーをシンプルにまとう上品なデザインでまとめている。傾斜した前面形状で運転台スペースが制約される中、高運転台構造を維持しつつ必要な機器を収めるため、前面貫通扉を正面から見て左側に配置した。正面窓下左右側に前照灯、尾灯、装飾灯からなる標識灯ユニットが配置されており、いずれの光源もLED照明。車体は溶接組立構造のステンレス製であり、外板をレーザー溶接でつなぎ合わせる総合車両製作所製のsustina構体を採用。これにより、これまでのステンレス車体に見られた板と板を重ねる「せぎり」がなくなり、車体全体を滑らかに美しく仕上げているとともに、連続したレーザー溶接によりシール部の施工箇所を削減することでメンテナンス性の向上を図っている。
20 m両開き4扉、扉間に窓2枚の基本レイアウトが採用されたが、扉間の窓2枚の幅は異なっており、広い方の窓のみ下降窓となっている。前頭部はFRP製で、先頭車運転台側は中間車より台車中心から車端までの長さが500mm延長された。スカートも3次元的形状となり、コーポレートカラーである京王レッドに塗装。前面窓上と、側面中央部窓上にフルカラーLED式の表示装置が設置され、側面のものは従来車より大型化。
内装
内装は高尾山の木々と織物の街・八王子の絹という多摩地域の色と素材にこだわった、華やかな室内空間を表現したデザインとしており、座席表皮は「多摩織」をモチーフとした上質な高級感を演出
。室内は上に行くほど色が明るくなっており、天井両側を凸曲面とすることで開放感がある室内空間とし、ガラス製の扉部仕切りと妻引戸の採用で奥行きのある開放感をもたせている。また車内の快適性を確保するため、床に静粛性の高い素材を、側窓にUVカットガラスをそれぞれ採用しており、手すりには清潔感を出すため電解加工を施して指紋が付きにくくしている。
京王電鉄の車両としては初めてクロスシートとロングシートの転換機構を備えたデュアルシートを採用し、座席指定列車として使用される際はクロスシート、それ以外のときは基本的にロングシートとなる。転換機構付き座席は総合車両製作所とコイト電工が共同開発し、コイト電工が製造を担当した。扉間には1人あたり座面幅460mmの偏心機構によって回転する2人掛け座席が片側3組配置されている。この座席は新規に開発が行われた座席であり、通勤電車として運用されるのと回転中の座席同士の干渉を避けるため、座席幅の確保については困難を極めたが、回転軌跡上にある窓枠下部の窓きせの形状の見直しとともに、2人掛座席の両側にある肘掛けの内側を削ることで1人あたり座面幅460mmを確保。クロスシート状態時の手動での座席転換は、肘掛けの後ろにあるレバーを引くことで座席が回転して転換する。
車端部には、総合車両製作所とシロキ工業が共同開発しシロキ工業が製造を担当した1人あたり座面幅505 mmの固定式3人掛け座席が設けられ、座席間には肘掛けが設置。座席座面と背もたれ下部は茶系の色の明暗により凹凸を表現したモケット織、背もたれ上部は濃い茶色のモール織が採用。全車両に設置された車椅子・ベビーカースペースには、壁掛け型のヒーターと立ち客が利用できる腰当てが設けられている。
室内灯は、総合車両製作所とコイト電工が共同開発しコイト電工が製造を担当したLED式の調光・調色式照明となり、朝の通勤時には爽やかな色、夜の座席指定列車時では落ち着いた暖色系の色に変えることが可能であり、天井両側の曲面部に照射するように配置した間接照明を採用している。クロスシートとロングシートのどちらで使用されている場合でも画面が見やすいよう、各扉上部と客室天井部の枕木方向に三菱電機製の17インチワイド液晶式案内装置が2台一組で各車両14組28台設置された。右側の画面には運行情報を、左側には広告が表示される。放送装置は、八幡電気産業製の高音質ステレオ方式を採用しており、ステレオ効果が最大限に得られるように車内スピーカーはKEF社製の物が1両あたり8台設置されている。天井面の左右にLとRが交互に配置されているほか、制御装置に音源を内蔵することで、イベント時にBGMを流すことができる。また、外部プレーヤが接続可能なステレオミニジャックを設けている。
サービス機器として、2人掛け座席の脚台および3人掛けロングシートの肘掛け部には、総合車両製作所とシロキ工業が共同開発しシロキ工業が製造を担当した電源コンセントが設けられ、UQコミュニケーションズ製フリーWi-Fi装置、パナソニックとJR東日本テクノロジーが共同開発した「nanoe(ナノイー)」搭載空気清浄機を天井中央部にあるラインフローファンのバックスペースに各2台設置されている。電源コンセントはクロスシートの時しか使えない設定となっている。各車両に4台ずつ日立造船製の逆光補正付き車内防犯カメラが設けられている。
客室扉の戸閉機は、京王電鉄としては初めてラック機構を有した電気式ドアエンジンを採用。ドアの挟まれを検知するとドアの推力を変化させて抜けやすくする戸挟み防止機能のほか、長時間の駅停車時の冷暖房効果を高めるための3扉閉機能のほかに、座席指定列車時での乗降をするドアを一部に限定にする限定扉機能を有している。
乗務員室
大きく傾斜した前面形状を採用しつつ、高運転台構造の維持と視界拡大、必要な機器の搭載などの要求を満足するため、機器配置の見直しと避難経路確保のための前面貫通路を正面向かって左側にするなど、従来車両とは乗務員室のレイアウトが大きく変更されている。運転室の配色はグレー系、運転台はユニットごとに取外しが可能な構造の総合車両製作所のユニット式運転台「フリージアコンソール」を採用。また、京王電鉄としては初めての採用となる3つの画面の運転台表示器を配置しており、速度計、圧力計、表示灯などの表示のほか、蓄電池とその残量、パンタグラフ、VVVFインバータ装置、主電動機との間で電気の流れを表示するエネルギーモニタ機能が備わっている。速度計や圧力計などの運転に必要な計器類は、従来のアナログ式を模した白背景の丸形計器のデザインとし、それらが、運転士の着座位置と主幹制御器の中心軸上に表示されるものとなった。
主幹制御器はデッドマン装置付きのT形ワンハンドルマスコンで、運転士の操作がロータリエンコーダにより信号に変換された後に二重系で出力され、各機器に伝送される。保安装置として、京三製作所製京王線内用ATCに加え、日立製作所製新宿線用D-ATCを装備する。新たにホーム検知装置(ジェイアール西日本テクノス製)が備えられている。これは、乗務員室の運転士背面の中央部にホームの検知状態を示す表示灯とドア開操作の誤操作を注意喚起するブザーで構成された報知盤が設置されており、ホームの有無を車両側のセンサーで検知して、ホームが検知できない側で誤ってドア開操作をしても、ドアの開操作は行われず、ブザーで注意喚起する。事故発生時の記録を目的として、両先頭車に日立造船製の前方監視カメラを設置している。
主要機器
伝送指令システム
京王電鉄で初めてサービス機器への指令のみならず力行・制動などの主要機器への指令も伝送指令とし、車両の引通し線の削減を図ったK-TIMS(Keio Train Information Management System)と呼ばれる三菱電機製の伝送指令システムを採用。システム全体が二重化されるとともに、主要機器への伝送経路も二重となっており、クロス/ロングシート転換座席の回転指令、室内LED灯の調光・調節指令、電源コンセントの入切指令、各機器の自動試験などがモニタ装置から実行できる。力行と回生ブレーキ時での主電動機のブレーキトルクを編成で一括管理して制御することで効率的で省エネルギー性の高い運転が可能としている。車両の車内案内装置を制御する編成間の伝送路には、K-TIMSと連携した100 Mbpsのイーサネット伝送が使用されている。
主制御装置、主電動機
定格3,300V・1,800AのSi-IGBT素子とSiC-SBD素子を組合わせたSiCハイブリッド素子による、日立製作所製VFI-HR2820W型VVVFインバータ制御装置が採用されている。1台の制御装置で4台の主電動機を制御する1C4M構成を1群としたものを2群搭載しており、制御方式は速度センサレスのベクトル制御としている。故障の際には2群のどちらかの1群(主電動機4台)の解放が可能な故障冗長性を持っており、全電気ブレーキと定速運転機能を持っている。デハ5000形に搭載されておりデハ5050形と電動車ユニットを組んでいる。
主電動機は出力150 kWの日立製作所製全閉型内扇冷却式かご形三相誘導電動機が、駆動装置は東洋電機製造製KD438-C-M形平行カルダン式(TD継手、TD230C-P)が採用されており、保守の軽減と騒音の低減を図っている。歯車比は85:14である。
さらなる省エネルギ性を推進する目的として新技術の車上蓄電システムを採用している。これは日立製作所製[22]のリチウムイオン電池を4直列4並列接続した680V、15.2kWhの電池モジュールを、編成中央の電動車(デハ5050形5100番台)1両の床下に2個搭載したものである。この蓄電システムには、ブレーキを掛けた際の回生ブレーキ時に主電動機から発生する電力を充電し、力行の時にはこれを走行用に放電することで電力消費量を削減する。また停電時には、この電池に蓄えられた電力を利用して1台のVVVFインバータ装置を起動することで編成内の電動車ユニット2両(1ユニット8モーター)を用いた自力走行が可能であり(この時では通常の6M4Tから2M8Tとなる)、橋梁上で列車が停止した場合などでも移動させることができる。
制動装置
制動装置は回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキのナブコ製HRDA-1が9000系に続いて採用されたが、弁制御をアナログ電流制御方式からON-OFF方制御弁に変更され、ブレーキ性能の安定性向上を図っており、K-TIMSの編成ブレーキ制御により付随車の制動力を電動車の回生ブレーキで負担する遅れ込め制御をユニットごとの制御から編成全体の制御に変更しており、回生ブレーキのさらなる有効性を図っている。また、Tc車とT車には、フラット防止機能(滑走再粘着制御)を有しており、車輪の滑走によるブレーキ距離の増大と車輪のフラット防止を図っている。
台車
台車は9000系用をベースとした総合車両製作所製の軸箱支持装置が軸梁式のボルスタレス空気ばねのTS-1017C動力台車、TS-1018C付随台車(いずれも固定軸距2,200 mm、車輪経860 mm)が採用された。台車の牽引力を車体に伝達するけん引装置は一本リンク式であり、基礎ブレーキ装置は、踏面片押し式のユニットブレーキ。将来の最高速度向上に備え、設計最高速度を130㎞/hとしており、さらなる乗り心地の向上のため、台車枠先端部と軸箱支持装置の軸梁の間に軸ダンパの取り付けが可能な構造となっている。
集電装置
集電装置として、9000系と同形式の東洋電機製造製電磁かぎ外し装置付きばね上昇空気式シングルアームパンタグラフがデハ5000形全車と、5100番台を除くデハ5050形に搭載された。
補助電源装置
補助電源装置は、東洋電機製造製60 Hz、440V、出力260kVAのIGBT素子の3レベル静止形インバータ (SIV)が5000番台と5200番台のデハ5050形に搭載されている。一系が故障した場合でも、待機している二系がバックアップとして作動する待機二重系方式を採用している、一系・二系の両方が故障した場合でも、乗務員室からのモニタ装置の操作により、6号車のデハ5000形に搭載された受給電接触器を作動させて、もう片方の補助電源装置からの給電を可能としている。
空気圧縮機
空気圧縮機は、ドイツ・クノールブレムゼ製のオイルフリーレシプロ方式を採用。毎分吐出容量1,750リットルの除湿装置内蔵ピストン式電動空気圧縮機はコンパクトで環境への配慮とメンテナンス性の向上を図っており、5000番台と5200番台のデハ5050形に搭載。
冷房装置
三菱電機製の屋上集中式58.14 kW (50,000 kcal/h) の冷房装置が各車に1台搭載されており、全自動運転を基本としているが、状況によりきめ細かい空調管理ができるように、乗務員室のモニタ装置の操作により、送風(換気)と除湿モードを手動で選択できるようにしている。
京王5000系 本八幡〜橋本.m4a
日中に運転が行われている都営新宿線 本八幡〜京王相模原線 橋本の運用を録音しました。都営新宿線は各停で京王線は区間急行となる。
〜京王5000系〜
外観
従来車両よりシャープで立体的な前面形状が採用されており、京王の車両としては初めて前面が大きく傾斜している。前面はスマートな列車を表現するためカラーリングに黒が多用され、窓上部に京王レッドの、窓下部に京王ブルーの帯が巻かれており、包容感を感じさせる温かみの中に気品のある表情を持たせ、コーポレートカラーをシンプルにまとう上品なデザインでまとめている。傾斜した前面形状で運転台スペースが制約される中、高運転台構造を維持しつつ必要な機器を収めるため、前面貫通扉を正面から見て左側に配置した。正面窓下左右側に前照灯、尾灯、装飾灯からなる標識灯ユニットが配置されており、いずれの光源もLED照明。車体は溶接組立構造のステンレス製であり、外板をレーザー溶接でつなぎ合わせる総合車両製作所製のsustina構体を採用。これにより、これまでのステンレス車体に見られた板と板を重ねる「せぎり」がなくなり、車体全体を滑らかに美しく仕上げているとともに、連続したレーザー溶接によりシール部の施工箇所を削減することでメンテナンス性の向上を図っている。
20 m両開き4扉、扉間に窓2枚の基本レイアウトが採用されたが、扉間の窓2枚の幅は異なっており、広い方の窓のみ下降窓となっている。前頭部はFRP製で、先頭車運転台側は中間車より台車中心から車端までの長さが500mm延長された。スカートも3次元的形状となり、コーポレートカラーである京王レッドに塗装。前面窓上と、側面中央部窓上にフルカラーLED式の表示装置が設置され、側面のものは従来車より大型化。
内装
内装は高尾山の木々と織物の街・八王子の絹という多摩地域の色と素材にこだわった、華やかな室内空間を表現したデザインとしており、座席表皮は「多摩織」をモチーフとした上質な高級感を演出
。室内は上に行くほど色が明るくなっており、天井両側を凸曲面とすることで開放感がある室内空間とし、ガラス製の扉部仕切りと妻引戸の採用で奥行きのある開放感をもたせている。また車内の快適性を確保するため、床に静粛性の高い素材を、側窓にUVカットガラスをそれぞれ採用しており、手すりには清潔感を出すため電解加工を施して指紋が付きにくくしている。
京王電鉄の車両としては初めてクロスシートとロングシートの転換機構を備えたデュアルシートを採用し、座席指定列車として使用される際はクロスシート、それ以外のときは基本的にロングシートとなる。転換機構付き座席は総合車両製作所とコイト電工が共同開発し、コイト電工が製造を担当した。扉間には1人あたり座面幅460mmの偏心機構によって回転する2人掛け座席が片側3組配置されている。この座席は新規に開発が行われた座席であり、通勤電車として運用されるのと回転中の座席同士の干渉を避けるため、座席幅の確保については困難を極めたが、回転軌跡上にある窓枠下部の窓きせの形状の見直しとともに、2人掛座席の両側にある肘掛けの内側を削ることで1人あたり座面幅460mmを確保。クロスシート状態時の手動での座席転換は、肘掛けの後ろにあるレバーを引くことで座席が回転して転換する。
車端部には、総合車両製作所とシロキ工業が共同開発しシロキ工業が製造を担当した1人あたり座面幅505 mmの固定式3人掛け座席が設けられ、座席間には肘掛けが設置。座席座面と背もたれ下部は茶系の色の明暗により凹凸を表現したモケット織、背もたれ上部は濃い茶色のモール織が採用。全車両に設置された車椅子・ベビーカースペースには、壁掛け型のヒーターと立ち客が利用できる腰当てが設けられている。
室内灯は、総合車両製作所とコイト電工が共同開発しコイト電工が製造を担当したLED式の調光・調色式照明となり、朝の通勤時には爽やかな色、夜の座席指定列車時では落ち着いた暖色系の色に変えることが可能であり、天井両側の曲面部に照射するように配置した間接照明を採用している。クロスシートとロングシートのどちらで使用されている場合でも画面が見やすいよう、各扉上部と客室天井部の枕木方向に三菱電機製の17インチワイド液晶式案内装置が2台一組で各車両14組28台設置された。右側の画面には運行情報を、左側には広告が表示される。放送装置は、八幡電気産業製の高音質ステレオ方式を採用しており、ステレオ効果が最大限に得られるように車内スピーカーはKEF社製の物が1両あたり8台設置されている。天井面の左右にLとRが交互に配置されているほか、制御装置に音源を内蔵することで、イベント時にBGMを流すことができる。また、外部プレーヤが接続可能なステレオミニジャックを設けている。
サービス機器として、2人掛け座席の脚台および3人掛けロングシートの肘掛け部には、総合車両製作所とシロキ工業が共同開発しシロキ工業が製造を担当した電源コンセントが設けられ、UQコミュニケーションズ製フリーWi-Fi装置、パナソニックとJR東日本テクノロジーが共同開発した「nanoe(ナノイー)」搭載空気清浄機を天井中央部にあるラインフローファンのバックスペースに各2台設置されている。電源コンセントはクロスシートの時しか使えない設定となっている。各車両に4台ずつ日立造船製の逆光補正付き車内防犯カメラが設けられている。
客室扉の戸閉機は、京王電鉄としては初めてラック機構を有した電気式ドアエンジンを採用。ドアの挟まれを検知するとドアの推力を変化させて抜けやすくする戸挟み防止機能のほか、長時間の駅停車時の冷暖房効果を高めるための3扉閉機能のほかに、座席指定列車時での乗降をするドアを一部に限定にする限定扉機能を有している。
乗務員室
大きく傾斜した前面形状を採用しつつ、高運転台構造の維持と視界拡大、必要な機器の搭載などの要求を満足するため、機器配置の見直しと避難経路確保のための前面貫通路を正面向かって左側にするなど、従来車両とは乗務員室のレイアウトが大きく変更されている。運転室の配色はグレー系、運転台はユニットごとに取外しが可能な構造の総合車両製作所のユニット式運転台「フリージアコンソール」を採用。また、京王電鉄としては初めての採用となる3つの画面の運転台表示器を配置しており、速度計、圧力計、表示灯などの表示のほか、蓄電池とその残量、パンタグラフ、VVVFインバータ装置、主電動機との間で電気の流れを表示するエネルギーモニタ機能が備わっている。速度計や圧力計などの運転に必要な計器類は、従来のアナログ式を模した白背景の丸形計器のデザインとし、それらが、運転士の着座位置と主幹制御器の中心軸上に表示されるものとなった。
主幹制御器はデッドマン装置付きのT形ワンハンドルマスコンで、運転士の操作がロータリエンコーダにより信号に変換された後に二重系で出力され、各機器に伝送される。保安装置として、京三製作所製京王線内用ATCに加え、日立製作所製新宿線用D-ATCを装備する。新たにホーム検知装置(ジェイアール西日本テクノス製)が備えられている。これは、乗務員室の運転士背面の中央部にホームの検知状態を示す表示灯とドア開操作の誤操作を注意喚起するブザーで構成された報知盤が設置されており、ホームの有無を車両側のセンサーで検知して、ホームが検知できない側で誤ってドア開操作をしても、ドアの開操作は行われず、ブザーで注意喚起する。事故発生時の記録を目的として、両先頭車に日立造船製の前方監視カメラを設置している。
主要機器
伝送指令システム
京王電鉄で初めてサービス機器への指令のみならず力行・制動などの主要機器への指令も伝送指令とし、車両の引通し線の削減を図ったK-TIMS(Keio Train Information Management System)と呼ばれる三菱電機製の伝送指令システムを採用。システム全体が二重化されるとともに、主要機器への伝送経路も二重となっており、クロス/ロングシート転換座席の回転指令、室内LED灯の調光・調節指令、電源コンセントの入切指令、各機器の自動試験などがモニタ装置から実行できる。力行と回生ブレーキ時での主電動機のブレーキトルクを編成で一括管理して制御することで効率的で省エネルギー性の高い運転が可能としている。車両の車内案内装置を制御する編成間の伝送路には、K-TIMSと連携した100 Mbpsのイーサネット伝送が使用されている。
主制御装置、主電動機
定格3,300V・1,800AのSi-IGBT素子とSiC-SBD素子を組合わせたSiCハイブリッド素子による、日立製作所製VFI-HR2820W型VVVFインバータ制御装置が採用されている。1台の制御装置で4台の主電動機を制御する1C4M構成を1群としたものを2群搭載しており、制御方式は速度センサレスのベクトル制御としている。故障の際には2群のどちらかの1群(主電動機4台)の解放が可能な故障冗長性を持っており、全電気ブレーキと定速運転機能を持っている。デハ5000形に搭載されておりデハ5050形と電動車ユニットを組んでいる。
主電動機は出力150 kWの日立製作所製全閉型内扇冷却式かご形三相誘導電動機が、駆動装置は東洋電機製造製KD438-C-M形平行カルダン式(TD継手、TD230C-P)が採用されており、保守の軽減と騒音の低減を図っている。歯車比は85:14である。
さらなる省エネルギ性を推進する目的として新技術の車上蓄電システムを採用している。これは日立製作所製[22]のリチウムイオン電池を4直列4並列接続した680V、15.2kWhの電池モジュールを、編成中央の電動車(デハ5050形5100番台)1両の床下に2個搭載したものである。この蓄電システムには、ブレーキを掛けた際の回生ブレーキ時に主電動機から発生する電力を充電し、力行の時にはこれを走行用に放電することで電力消費量を削減する。また停電時には、この電池に蓄えられた電力を利用して1台のVVVFインバータ装置を起動することで編成内の電動車ユニット2両(1ユニット8モーター)を用いた自力走行が可能であり(この時では通常の6M4Tから2M8Tとなる)、橋梁上で列車が停止した場合などでも移動させることができる。
制動装置
制動装置は回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキのナブコ製HRDA-1が9000系に続いて採用されたが、弁制御をアナログ電流制御方式からON-OFF方制御弁に変更され、ブレーキ性能の安定性向上を図っており、K-TIMSの編成ブレーキ制御により付随車の制動力を電動車の回生ブレーキで負担する遅れ込め制御をユニットごとの制御から編成全体の制御に変更しており、回生ブレーキのさらなる有効性を図っている。また、Tc車とT車には、フラット防止機能(滑走再粘着制御)を有しており、車輪の滑走によるブレーキ距離の増大と車輪のフラット防止を図っている。
台車
台車は9000系用をベースとした総合車両製作所製の軸箱支持装置が軸梁式のボルスタレス空気ばねのTS-1017C動力台車、TS-1018C付随台車(いずれも固定軸距2,200 mm、車輪経860 mm)が採用された。台車の牽引力を車体に伝達するけん引装置は一本リンク式であり、基礎ブレーキ装置は、踏面片押し式のユニットブレーキ。将来の最高速度向上に備え、設計最高速度を130㎞/hとしており、さらなる乗り心地の向上のため、台車枠先端部と軸箱支持装置の軸梁の間に軸ダンパの取り付けが可能な構造となっている。
集電装置
集電装置として、9000系と同形式の東洋電機製造製電磁かぎ外し装置付きばね上昇空気式シングルアームパンタグラフがデハ5000形全車と、5100番台を除くデハ5050形に搭載された。
補助電源装置
補助電源装置は、東洋電機製造製60 Hz、440V、出力260kVAのIGBT素子の3レベル静止形インバータ (SIV)が5000番台と5200番台のデハ5050形に搭載されている。一系が故障した場合でも、待機している二系がバックアップとして作動する待機二重系方式を採用している、一系・二系の両方が故障した場合でも、乗務員室からのモニタ装置の操作により、6号車のデハ5000形に搭載された受給電接触器を作動させて、もう片方の補助電源装置からの給電を可能としている。
空気圧縮機
空気圧縮機は、ドイツ・クノールブレムゼ製のオイルフリーレシプロ方式を採用。毎分吐出容量1,750リットルの除湿装置内蔵ピストン式電動空気圧縮機はコンパクトで環境への配慮とメンテナンス性の向上を図っており、5000番台と5200番台のデハ5050形に搭載。
冷房装置
三菱電機製の屋上集中式58.14 kW (50,000 kcal/h) の冷房装置が各車に1台搭載されており、全自動運転を基本としているが、状況によりきめ細かい空調管理ができるように、乗務員室のモニタ装置の操作により、送風(換気)と除湿モードを手動で選択できるようにしている。 京急新1000形(アルミ車)横浜ー三崎口.MP3
〜京急新1000形(アルミ車)について〜
車体
車体はアルミニウム合金製で、外観は2100形と同じく側面の窓周りを広幅に白く塗る塗り分け。
VVVFインバータ制御装置は、1・2次車では2100形と同じくGTOサイリスタ素子によるドイツ・SIEMENS社製を採用、3~5次車では同じシーメンス社製であるが、使用素子はIGBTに変更され、純電気ブレーキも搭載。
2002(平成14)年度製の1次車の側面窓は一段下降式の分割窓で登場したが、2003(平成15)年度製の2次車からは側面窓が黒い大型窓となり、種別・行先表示器にローマ字を併記の上、行先表示器の字幕下地の色を白とした。
2005(平成17)年度製の4次車からは種別表示器がフルカラーLED式、行先表示器が白色LED式、運行番号表示器がオレンジ色LED式となった。前面行先表示器はローマ字表記を省略、側面行先表示器はローマ字併記とされたが、側面については行先とローマ字と交互に表示されるよう変更された。
車内
車内は、1~5次車については扉間は脚台をなくした片持ち式ロングシート、車端部が補助いす付きのクロスシートとなっている。
2010(平成22)年度製車両よりドア上部へ液晶モニタ(LCD・17インチワイド形)方式の車内案内表示器(映像情報配信装置・トレインビジョン・VIS)を設置、さらにドア上部点検フタ下部にドア開閉表示灯(ドア開閉時に赤く点滅)やドア全開時に開扉チャイムを追加。運転台では乗務員支援や誤通過防止機能を有する車上情報管理装置を搭載し、運転台計器盤右端にモニター画面を設置した。
台車
円筒案内支持方式空気バネ台車のTH-2100A形・TH-2100B形を使用。
制御装置など
主電動機はかご形三相誘導電動機。主電動機の出力は190 kWとなっている。
駆動方式はTD継手式平行カルダンを採用。
制御方式 GTO、IGBT素子によるVVVFインバータ制御。
ブレーキは応荷重装置付回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキを使用している。
保安装置は1号型ATS、C-ATS。
京急新1000形(アルミ車)横浜ー三崎口.MP3
〜京急新1000形(アルミ車)について〜
車体
車体はアルミニウム合金製で、外観は2100形と同じく側面の窓周りを広幅に白く塗る塗り分け。
VVVFインバータ制御装置は、1・2次車では2100形と同じくGTOサイリスタ素子によるドイツ・SIEMENS社製を採用、3~5次車では同じシーメンス社製であるが、使用素子はIGBTに変更され、純電気ブレーキも搭載。
2002(平成14)年度製の1次車の側面窓は一段下降式の分割窓で登場したが、2003(平成15)年度製の2次車からは側面窓が黒い大型窓となり、種別・行先表示器にローマ字を併記の上、行先表示器の字幕下地の色を白とした。
2005(平成17)年度製の4次車からは種別表示器がフルカラーLED式、行先表示器が白色LED式、運行番号表示器がオレンジ色LED式となった。前面行先表示器はローマ字表記を省略、側面行先表示器はローマ字併記とされたが、側面については行先とローマ字と交互に表示されるよう変更された。
車内
車内は、1~5次車については扉間は脚台をなくした片持ち式ロングシート、車端部が補助いす付きのクロスシートとなっている。
2010(平成22)年度製車両よりドア上部へ液晶モニタ(LCD・17インチワイド形)方式の車内案内表示器(映像情報配信装置・トレインビジョン・VIS)を設置、さらにドア上部点検フタ下部にドア開閉表示灯(ドア開閉時に赤く点滅)やドア全開時に開扉チャイムを追加。運転台では乗務員支援や誤通過防止機能を有する車上情報管理装置を搭載し、運転台計器盤右端にモニター画面を設置した。
台車
円筒案内支持方式空気バネ台車のTH-2100A形・TH-2100B形を使用。
制御装置など
主電動機はかご形三相誘導電動機。主電動機の出力は190 kWとなっている。
駆動方式はTD継手式平行カルダンを採用。
制御方式 GTO、IGBT素子によるVVVFインバータ制御。
ブレーキは応荷重装置付回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキを使用している。
保安装置は1号型ATS、C-ATS。
 京急2100形 横浜ー三崎口.mp3
〜京急2100形について〜
外観
車体外板は赤、窓回りをアイボリーに塗装している。前面デザインは600形をベースとし、「都会」・「洗練」・「知的」と「スピード感」をイメージした流線型形状とし、21世紀に向かう京急のイメージリーダーにふさわしい車両を目指した。先頭車正面窓下アイボリー塗装のワイパーカバーには、形式名(2100)がスリット状の打ち抜き文字で表現されている。これは分割併合時にスリットを通して連結器を見通せるようにしたためである。
1500形アルミ車と600形で採用したLED表示灯は経年変化による照度低下が著しく、また電球の寿命も延びたことから尾灯・急行灯および戸閉灯が2灯の電球となった。尾灯と急行灯の位置は4次車で逆転し、それ以前の編成も変更した。車両間には新たに転落防止幌が設置された。正面のスカートは600形のものと類似した形状であるが、600形のものと比較して横幅が狭くなっている。
内装
内装のコンセプトはCasual&Free/「若者と自然のエリア」とし、メルティな乗り心地、ソフトでやさしい、深く透き通るような客室空間を演出。
車内は淡い琥珀色の大理石模様化粧板張りとし、連結面の妻壁は淡いパープル系の化粧シート仕上げとした。車椅子スペースは先頭車の乗務員室次位の扉直後に設置をしている。
天井部はFRP製の曲面天井構成で、補助送風機はなく、空調吹き出し口を設置するのみである。車内蛍光灯にはアクリル製のカバー付蛍光灯を使用している。
床材は新造車としては初めての塗り床構造とし、ベージュとレッド系のモザイク柄としている。電動車の床面には600形と同様に駆動装置点検蓋が設置されているが、点検ブタは縁取りをなくし、床面のフラット化を図った。
側窓・扉類
側窓はすべて濃色グレーの熱線吸収・複層ガラス構成とし、結露防止と空調の効率化のために全てが固定窓である。カーテンにはパープル系色の西陣織の横引き式プリーツカーテンを設置する。なお、全ての窓が固定式のため、非常時の換気のため、各車2台排気扇を設置している。
側扉と連結面貫通扉は軽量化のためにペーパーハニカム構造を採用。貫通扉は各連結面に設置しており、側扉については室内側は化粧板仕上げ、ドアガラスは側窓同様のグレーの複層ガラスである。各扉上部には京急初採用となるLED文字スクロール表示による車内案内表示器を設置している。
座席について
料金不要の特急車両として上質なサービスを提供している。室内はオールクロスシートで、ドア間は京急で初採用となる転換クロスシート、車端部は4人掛けボックスシート(固定座席)である。先頭車の運転席背面は前向きの固定座席としており、運転席背後以外のドア前には補助腰掛を設置している。
空港連絡列車に使用することを考慮し、一部の固定座席は座面を上げて荷物置場にできる構造となっている。ドア間の座席はノルウェー・エクネス社 (Georg Eknes) 製、座席表地はスウェーデン・ボーゲサンズ社 (Bogesunds) 製である。座席はいずれも瑠璃色(紺色系)に茜色(赤色)の水玉模様入りジャカード織(模様入り)で、枕カバーは一般席が赤色、優先席は灰色系で区別している。
転換クロスシート部は座席を向かい合わせで用いないことを前提に間隔を詰めており、シートピッチは850 mmである。営業運転中は一方に向きが固定され、乗客による座席の転換はできない。座席の転換は空気圧による一括転換式を採用しており、始発駅で車掌のスイッチ操作により進行方向へ座席の向きを合わせる。終着駅に到着した際は、到着ホームでそのまま折り返す場合も降車扱いの後ドアを閉め、座席転換後に乗車扱いをする措置がとられている。
転換クロスシートは関東の大手私鉄では唯一のものである。しかし、座席に掴み手がつけられているもののつり革はドア周辺のみの設置で、通路も狭くなっている。
補助腰掛は出入口と転換腰掛を仕切る壁としての役割がある。背ずりは固定されており、座面が手前に引き出してくる形状である。乗務員室からの操作で鎖錠・解錠が可能で、混雑時には固定され、閑散時は引き出して使用することができる。
電装品
主制御器はVVVFインバータ装置、フィルターリアクトル、断流器などを「トラクションコンテナ」と呼ばれる一体箱に収めた構成とした。また、この制御装置はベクトル制御やスリップ・スライド制御(空転滑走制御)など高い精度での電動機のトルク制御を行い、本系式の高い性能を実現している。
主制御器形式:G1450D1130/560M5-1形(1C4M制御方式、容量1,096 kVA、耐圧4,500 V、電流3,000 A、周波数0 - 163 Hz、質量1,700 kg)
主電動機:1TB2010-0GC02形かご形三相誘導電動機(出力190 kW、端子電圧1,050 V、電流133 A、周波数61 Hz、定格回転数1,800 rpm、最高回転数5,243 rpm、質量550 kg :全て1時間定格ではなく、連続定格値)
1:1というMT比で高速性能と高加速度を両立するため、高出力のかご形三相誘導電動機が用いられている。なお、電動機の京急における制式名称はKHM-2100形である。
台車は空気バネ(枕バネ)を車体に直結させるダイレクトマウント式のボルスタ(枕梁)付き台車であり、軸箱支持方式は高速走行時の乗り心地の観点から乾式ゴム入りの円筒案内式である。動力台車は「TH-2100M形」、付随台車は「TH-2100T形」。
補助電源装置にはIGBT素子を使用した三菱電機製の150 kVA出力静止形インバータ(NC-WAT150C形)で、本形式より車内の低圧補助回路の電圧を三相交流440Vへと向上。
電動空気圧縮機にはドイツ・クノールブレムゼ社製のスクリュー式(SL-22形、吐出量は1600 L/min)が採用。集電装置は東洋電機製造製のPT7117-A形シングアーム式を使用している。
空調装置は三菱電機製のCU-71G形を使用し、能力は41.8 kW(36,000 kcal/h)としている。外観では装置の前後にFRP製の曲面カバーを設置し、丸みを強調したものとした。
京急2100形 横浜ー三崎口.mp3
〜京急2100形について〜
外観
車体外板は赤、窓回りをアイボリーに塗装している。前面デザインは600形をベースとし、「都会」・「洗練」・「知的」と「スピード感」をイメージした流線型形状とし、21世紀に向かう京急のイメージリーダーにふさわしい車両を目指した。先頭車正面窓下アイボリー塗装のワイパーカバーには、形式名(2100)がスリット状の打ち抜き文字で表現されている。これは分割併合時にスリットを通して連結器を見通せるようにしたためである。
1500形アルミ車と600形で採用したLED表示灯は経年変化による照度低下が著しく、また電球の寿命も延びたことから尾灯・急行灯および戸閉灯が2灯の電球となった。尾灯と急行灯の位置は4次車で逆転し、それ以前の編成も変更した。車両間には新たに転落防止幌が設置された。正面のスカートは600形のものと類似した形状であるが、600形のものと比較して横幅が狭くなっている。
内装
内装のコンセプトはCasual&Free/「若者と自然のエリア」とし、メルティな乗り心地、ソフトでやさしい、深く透き通るような客室空間を演出。
車内は淡い琥珀色の大理石模様化粧板張りとし、連結面の妻壁は淡いパープル系の化粧シート仕上げとした。車椅子スペースは先頭車の乗務員室次位の扉直後に設置をしている。
天井部はFRP製の曲面天井構成で、補助送風機はなく、空調吹き出し口を設置するのみである。車内蛍光灯にはアクリル製のカバー付蛍光灯を使用している。
床材は新造車としては初めての塗り床構造とし、ベージュとレッド系のモザイク柄としている。電動車の床面には600形と同様に駆動装置点検蓋が設置されているが、点検ブタは縁取りをなくし、床面のフラット化を図った。
側窓・扉類
側窓はすべて濃色グレーの熱線吸収・複層ガラス構成とし、結露防止と空調の効率化のために全てが固定窓である。カーテンにはパープル系色の西陣織の横引き式プリーツカーテンを設置する。なお、全ての窓が固定式のため、非常時の換気のため、各車2台排気扇を設置している。
側扉と連結面貫通扉は軽量化のためにペーパーハニカム構造を採用。貫通扉は各連結面に設置しており、側扉については室内側は化粧板仕上げ、ドアガラスは側窓同様のグレーの複層ガラスである。各扉上部には京急初採用となるLED文字スクロール表示による車内案内表示器を設置している。
座席について
料金不要の特急車両として上質なサービスを提供している。室内はオールクロスシートで、ドア間は京急で初採用となる転換クロスシート、車端部は4人掛けボックスシート(固定座席)である。先頭車の運転席背面は前向きの固定座席としており、運転席背後以外のドア前には補助腰掛を設置している。
空港連絡列車に使用することを考慮し、一部の固定座席は座面を上げて荷物置場にできる構造となっている。ドア間の座席はノルウェー・エクネス社 (Georg Eknes) 製、座席表地はスウェーデン・ボーゲサンズ社 (Bogesunds) 製である。座席はいずれも瑠璃色(紺色系)に茜色(赤色)の水玉模様入りジャカード織(模様入り)で、枕カバーは一般席が赤色、優先席は灰色系で区別している。
転換クロスシート部は座席を向かい合わせで用いないことを前提に間隔を詰めており、シートピッチは850 mmである。営業運転中は一方に向きが固定され、乗客による座席の転換はできない。座席の転換は空気圧による一括転換式を採用しており、始発駅で車掌のスイッチ操作により進行方向へ座席の向きを合わせる。終着駅に到着した際は、到着ホームでそのまま折り返す場合も降車扱いの後ドアを閉め、座席転換後に乗車扱いをする措置がとられている。
転換クロスシートは関東の大手私鉄では唯一のものである。しかし、座席に掴み手がつけられているもののつり革はドア周辺のみの設置で、通路も狭くなっている。
補助腰掛は出入口と転換腰掛を仕切る壁としての役割がある。背ずりは固定されており、座面が手前に引き出してくる形状である。乗務員室からの操作で鎖錠・解錠が可能で、混雑時には固定され、閑散時は引き出して使用することができる。
電装品
主制御器はVVVFインバータ装置、フィルターリアクトル、断流器などを「トラクションコンテナ」と呼ばれる一体箱に収めた構成とした。また、この制御装置はベクトル制御やスリップ・スライド制御(空転滑走制御)など高い精度での電動機のトルク制御を行い、本系式の高い性能を実現している。
主制御器形式:G1450D1130/560M5-1形(1C4M制御方式、容量1,096 kVA、耐圧4,500 V、電流3,000 A、周波数0 - 163 Hz、質量1,700 kg)
主電動機:1TB2010-0GC02形かご形三相誘導電動機(出力190 kW、端子電圧1,050 V、電流133 A、周波数61 Hz、定格回転数1,800 rpm、最高回転数5,243 rpm、質量550 kg :全て1時間定格ではなく、連続定格値)
1:1というMT比で高速性能と高加速度を両立するため、高出力のかご形三相誘導電動機が用いられている。なお、電動機の京急における制式名称はKHM-2100形である。
台車は空気バネ(枕バネ)を車体に直結させるダイレクトマウント式のボルスタ(枕梁)付き台車であり、軸箱支持方式は高速走行時の乗り心地の観点から乾式ゴム入りの円筒案内式である。動力台車は「TH-2100M形」、付随台車は「TH-2100T形」。
補助電源装置にはIGBT素子を使用した三菱電機製の150 kVA出力静止形インバータ(NC-WAT150C形)で、本形式より車内の低圧補助回路の電圧を三相交流440Vへと向上。
電動空気圧縮機にはドイツ・クノールブレムゼ社製のスクリュー式(SL-22形、吐出量は1600 L/min)が採用。集電装置は東洋電機製造製のPT7117-A形シングアーム式を使用している。
空調装置は三菱電機製のCU-71G形を使用し、能力は41.8 kW(36,000 kcal/h)としている。外観では装置の前後にFRP製の曲面カバーを設置し、丸みを強調したものとした。 京急新1000形1800番台 新逗子〜金沢文庫.mp3
逗子線で録音。新逗子→金沢文庫のみの運用で、金沢文庫到着後は車庫へと引き上げる。
【京急新1000形1800番台】
1361編成は14次車からの変更点はないが、1367編成では東芝製SEA-548 永久磁石同期電動機(PMSM)と4台の主電動機を1台で制御するSVF102-G0主制御装置が採用。主電動機出力は190kWとされた。
4両編成は、浅草線直通用の8両編成が不足した際に2編成を連結して直通運用に使用できるよう先頭車前面の貫通扉が車体中央に移設され、貫通路として使用できるよう各部の仕様が変更された。車両番号も「1800番台」に区分されている。2編成を貫通する際は、正面貫通扉、折り戸を使用して運転席を仕切るとともに、床面との段差解消のためのスロープと一体化した渡り板と貫通幌を取り付けることで編成間の通路を構成する。貫通路を使用しない場合は渡り板を取り外す必要があるが、幌を取り付けたまま走行できるよう金具で固定されている。運転室と客室の間の仕切り扉は貫通路を使用した際、車両間を自動で仕切らなければならない新火災対策への対応の容易化から引き戸とされ、戸袋の確保のため非常脱出用梯子の収納部が客室側に張り出す構造となった。運転席のスイッチ類の一部は壁面に移設され、従来運転席コンソールに埋め込まれていたモニタも別体化されて上方に移動している。標識灯・尾灯は従来電球の交換容易化のため車体内側から取り付けられていたが、運転台構造の変更により内側からアクセスできなくなったため、外側から取り付ける構造に変更の上、電球交換の頻度を減らすため、LED化された。LEDは新開発の電球色のものが採用された。
伝統的な塗装を再現したい、との社内要望を受け、ステンレス製のまま塗装することも検討されたが、コストやメンテナンスで有利な幅広の赤色と白色のカラーフィルムが貼付されている。窓枠や客室扉と乗務員室扉の周りは曲線がきつくカラーフィルムが貼れないこと、洗車時にはがれやすくなることからフィルムは貼付されていない。
京急新1000形1800番台 新逗子〜金沢文庫.mp3
逗子線で録音。新逗子→金沢文庫のみの運用で、金沢文庫到着後は車庫へと引き上げる。
【京急新1000形1800番台】
1361編成は14次車からの変更点はないが、1367編成では東芝製SEA-548 永久磁石同期電動機(PMSM)と4台の主電動機を1台で制御するSVF102-G0主制御装置が採用。主電動機出力は190kWとされた。
4両編成は、浅草線直通用の8両編成が不足した際に2編成を連結して直通運用に使用できるよう先頭車前面の貫通扉が車体中央に移設され、貫通路として使用できるよう各部の仕様が変更された。車両番号も「1800番台」に区分されている。2編成を貫通する際は、正面貫通扉、折り戸を使用して運転席を仕切るとともに、床面との段差解消のためのスロープと一体化した渡り板と貫通幌を取り付けることで編成間の通路を構成する。貫通路を使用しない場合は渡り板を取り外す必要があるが、幌を取り付けたまま走行できるよう金具で固定されている。運転室と客室の間の仕切り扉は貫通路を使用した際、車両間を自動で仕切らなければならない新火災対策への対応の容易化から引き戸とされ、戸袋の確保のため非常脱出用梯子の収納部が客室側に張り出す構造となった。運転席のスイッチ類の一部は壁面に移設され、従来運転席コンソールに埋め込まれていたモニタも別体化されて上方に移動している。標識灯・尾灯は従来電球の交換容易化のため車体内側から取り付けられていたが、運転台構造の変更により内側からアクセスできなくなったため、外側から取り付ける構造に変更の上、電球交換の頻度を減らすため、LED化された。LEDは新開発の電球色のものが採用された。
伝統的な塗装を再現したい、との社内要望を受け、ステンレス製のまま塗装することも検討されたが、コストやメンテナンスで有利な幅広の赤色と白色のカラーフィルムが貼付されている。窓枠や客室扉と乗務員室扉の周りは曲線がきつくカラーフィルムが貼れないこと、洗車時にはがれやすくなることからフィルムは貼付されていない。 JRN700系 京都〜新横浜.mp3
ひかり530号に乗車し、録音しました。
〜JRN700系について〜
車体は、700系と同じくアルミニウム合金製の中空押出型材によるダブルスキン構造を採用。700系では、屋根構体、客室部の側構体のみであったが、N700系では使用範囲を広げ、車端部の側構体や妻構体、台車上部の気密床にも使用している。車体断面は700系よりも屋根肩が角張った形となったが、引き続き幕板部分がわずかながらも曲面となっている。
先頭部は、700系のエアロストリーム型を遺伝的アルゴリズムにより改良した「エアロ・ダブルウィング」という形状で、長さは10.7m(500系は15m、700系は9.2m)である。騒音対策と製作・保守費用低減を両立するため、扉は両先頭車の運転室側にある乗務員用と客用のみプラグドア、その他はすべて通常の引き戸が採用されている。その引き戸の開口部も、従来の0系から700系、800系(500系は全車プラグドアのため例外)では車体に別製作の枠をビス止めする構造だったが、本系列では平滑化のため構体が継ぎ目なく開口部を形成している。ドア回り戸袋側に見られるビスは、ドア用ゴムパッキンを着脱するためのものであり、構体とは無関係。
運転室部分の窓は、車体の絞り込み部分に掛かるため、700系よりも前面窓の開口部面積が特に左右方向に対して小さくなっており、前方視界は狭くなっている。
先頭車両の高さは、3,500mmの部分と3,600mmの部分がある。そのため、先頭車両編成中央寄りの客用扉付近の屋根には段差がある。中間車両高さは3,600mmとなっている。この段差は先頭車の車体断面積を削減し前頭部分の形状と合わせた微気圧波軽減の実現と、空気抵抗軽減などを目的とした空力上の処理である。
また、500系まで乗務員用扉横の握り棒は金属の手すりを埋め込む構造だったが、700系からは走行中の空気抵抗を低減するため、カバーを設置し走行中は自動的にせり上がる平滑把手を採用。本系列も同様であるが、700系では5km/hでカバーされるのに対し、本系列では70km/hとなっている。これは、ホームを出線するまで、最後尾車両の乗務員が手すりを握って安全確認をできるようにするためである。
走行機器
かご形三相誘導電動機を電動車両1両あたり4基搭載する。高さ60cm、長さ69cm、幅71cm、重量396kgである。4000番台の主電動機は東洋電機製造株式会社により製造された。M'車に主変圧器、M1車に主変換装置を1台、M2車に主変換装置を2台搭載しており、M1車は自車の主電動機4個を制御するが、M2車は自車と隣りのM'車の主電動機8個を制御する。
3M用の主変圧器(形式名:TTM5/WTM208)は1次容量は4,350kVAとし、4M用の主変圧器(形式名:TTM4/WTM207)は1次容量5,600kVAとしている。
主変換装置1台で並列接続された4台の主電動機を制御する。主変換装置の半導体素子の冷却方式は、大きく2種類に分けられ、電動車両が3両のユニットには、走行中に受ける床下の走行風で冷却する走行風冷却方式(形式名:TCI100/WPC203)、電動車両が4両のユニットには内蔵されたブロアでの冷却による強制風冷沸騰冷却方式(形式名:TCI3/WPC202)を搭載されている。
ブレーキシステムは、制御応答性に優れる回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ方式を採用する。
集電装置
集電装置(TPS303/WPS206)はシングルアーム形パンタグラフであるが、従来の700系などに見られるタイプより下枠(関節部分より下側)のアームが極端に短くなり、その関節部と下枠部分も流線型のカバーで完全に覆われた新開発のパンタグラフを採用している。これによって従来のシングルアームパンタグラフよりも風切り音の軽減と、架線への追随性の一層の向上を果たしている。
碍子覆いと二面側壁の形状は700系とほぼ同一で、碍子覆いの両側に大型の二面側壁を設けている。この二面側壁の全長は700系のものより延長され、傾斜角も緩やかなものとなっている。またEGS投入目視確認用の小窓が無くなり、かわりにEGSの投入状態を監視するカメラが碍子覆い内に、モニターが各パンタグラフ搭載号車の車内に設置された。この碍子覆いと二面側壁はアルミニウムハニカムパネル、炭素繊維強化プラスチックパネルを使用することで軽量化を実現。
700系では16両編成の場合4両おき(4 - 5, 8 - 9, 12 - 13号車間)に設置されていた高圧引き通し線のケーブルヘッドは、編成中間の1箇所のみの設置に削減され、他の車両間では直ジョイントによる接続となっている。
行先表示器・座席指定表示器
JR東海の営業用新幹線車両では初めてフルカラーLED式行先表示器とHIDランプによる標識灯を採用。行先表示器は全車両に設置され、表示内容は列車名・行先・指定席/自由席の種別を日本語、英語の順に表示し、日本語で列車名・行先表示とともに、始発駅では停車駅をスクロール表示させ、途中駅では次の停車駅を表示する。座席指定表示器も700系C編成までの液晶からLEDに変更され、「指定席」は緑色、「自由席」は白色表示となっている
JRN700系 京都〜新横浜.mp3
ひかり530号に乗車し、録音しました。
〜JRN700系について〜
車体は、700系と同じくアルミニウム合金製の中空押出型材によるダブルスキン構造を採用。700系では、屋根構体、客室部の側構体のみであったが、N700系では使用範囲を広げ、車端部の側構体や妻構体、台車上部の気密床にも使用している。車体断面は700系よりも屋根肩が角張った形となったが、引き続き幕板部分がわずかながらも曲面となっている。
先頭部は、700系のエアロストリーム型を遺伝的アルゴリズムにより改良した「エアロ・ダブルウィング」という形状で、長さは10.7m(500系は15m、700系は9.2m)である。騒音対策と製作・保守費用低減を両立するため、扉は両先頭車の運転室側にある乗務員用と客用のみプラグドア、その他はすべて通常の引き戸が採用されている。その引き戸の開口部も、従来の0系から700系、800系(500系は全車プラグドアのため例外)では車体に別製作の枠をビス止めする構造だったが、本系列では平滑化のため構体が継ぎ目なく開口部を形成している。ドア回り戸袋側に見られるビスは、ドア用ゴムパッキンを着脱するためのものであり、構体とは無関係。
運転室部分の窓は、車体の絞り込み部分に掛かるため、700系よりも前面窓の開口部面積が特に左右方向に対して小さくなっており、前方視界は狭くなっている。
先頭車両の高さは、3,500mmの部分と3,600mmの部分がある。そのため、先頭車両編成中央寄りの客用扉付近の屋根には段差がある。中間車両高さは3,600mmとなっている。この段差は先頭車の車体断面積を削減し前頭部分の形状と合わせた微気圧波軽減の実現と、空気抵抗軽減などを目的とした空力上の処理である。
また、500系まで乗務員用扉横の握り棒は金属の手すりを埋め込む構造だったが、700系からは走行中の空気抵抗を低減するため、カバーを設置し走行中は自動的にせり上がる平滑把手を採用。本系列も同様であるが、700系では5km/hでカバーされるのに対し、本系列では70km/hとなっている。これは、ホームを出線するまで、最後尾車両の乗務員が手すりを握って安全確認をできるようにするためである。
走行機器
かご形三相誘導電動機を電動車両1両あたり4基搭載する。高さ60cm、長さ69cm、幅71cm、重量396kgである。4000番台の主電動機は東洋電機製造株式会社により製造された。M'車に主変圧器、M1車に主変換装置を1台、M2車に主変換装置を2台搭載しており、M1車は自車の主電動機4個を制御するが、M2車は自車と隣りのM'車の主電動機8個を制御する。
3M用の主変圧器(形式名:TTM5/WTM208)は1次容量は4,350kVAとし、4M用の主変圧器(形式名:TTM4/WTM207)は1次容量5,600kVAとしている。
主変換装置1台で並列接続された4台の主電動機を制御する。主変換装置の半導体素子の冷却方式は、大きく2種類に分けられ、電動車両が3両のユニットには、走行中に受ける床下の走行風で冷却する走行風冷却方式(形式名:TCI100/WPC203)、電動車両が4両のユニットには内蔵されたブロアでの冷却による強制風冷沸騰冷却方式(形式名:TCI3/WPC202)を搭載されている。
ブレーキシステムは、制御応答性に優れる回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ方式を採用する。
集電装置
集電装置(TPS303/WPS206)はシングルアーム形パンタグラフであるが、従来の700系などに見られるタイプより下枠(関節部分より下側)のアームが極端に短くなり、その関節部と下枠部分も流線型のカバーで完全に覆われた新開発のパンタグラフを採用している。これによって従来のシングルアームパンタグラフよりも風切り音の軽減と、架線への追随性の一層の向上を果たしている。
碍子覆いと二面側壁の形状は700系とほぼ同一で、碍子覆いの両側に大型の二面側壁を設けている。この二面側壁の全長は700系のものより延長され、傾斜角も緩やかなものとなっている。またEGS投入目視確認用の小窓が無くなり、かわりにEGSの投入状態を監視するカメラが碍子覆い内に、モニターが各パンタグラフ搭載号車の車内に設置された。この碍子覆いと二面側壁はアルミニウムハニカムパネル、炭素繊維強化プラスチックパネルを使用することで軽量化を実現。
700系では16両編成の場合4両おき(4 - 5, 8 - 9, 12 - 13号車間)に設置されていた高圧引き通し線のケーブルヘッドは、編成中間の1箇所のみの設置に削減され、他の車両間では直ジョイントによる接続となっている。
行先表示器・座席指定表示器
JR東海の営業用新幹線車両では初めてフルカラーLED式行先表示器とHIDランプによる標識灯を採用。行先表示器は全車両に設置され、表示内容は列車名・行先・指定席/自由席の種別を日本語、英語の順に表示し、日本語で列車名・行先表示とともに、始発駅では停車駅をスクロール表示させ、途中駅では次の停車駅を表示する。座席指定表示器も700系C編成までの液晶からLEDに変更され、「指定席」は緑色、「自由席」は白色表示となっている JR221系 奈良〜JR難波.mp3
関西本線(大和路線)で録音をしました。
ーJR西日本221系についてー
車体
車体長は19,670/19,500mm(先頭車/中間車)、車体幅は2,950mm、20m級車体に片側3箇所の両開き扉(開き幅1,300mm)という、近郊形としてはオーソドックスな構成。ただし、113系・115系と比較して両端の側出入口の位置を若干車端に寄せており、制御電動車・制御車の場合は運転台直後に乗降扉が配置される。
車体は普通鋼製である。台枠は、側梁と横梁に一般構造用圧延鋼材 (SS400)、枕梁と中梁に溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 (SMA50B) および高耐候性圧延鋼材 (SPA) を使用した溶接組立構造。側面窓に大型連続窓を採用したことから、腐食防止を考慮して外板には耐候性圧延鋼材 (SPA) を使用し、板厚は側腰板が2.3mm、幕板が1.6mmである。屋根板は、0.6mm厚のステンレス鋼 (SUS) 波板および1.6mm厚の SPA を使用し、ポリウレタン樹脂による塗り屋根としている。床には1.0mm厚のSUS波板を使用する。
床面高さはホームとの段差を小さくするために1,150mm(117系比75mm縮小)とし、屋根高さを46mm上昇、天井機器の小型化により客室高さを
2,330mm(117系比160mm拡大)とした。
種別・行先表示器
車両正面には、列車種別のみを字幕式で表示しているのみで、列車の行先を表示する装置はない。側面の行先表示器は、列車種別を回転式字幕で、行先と号車番号を発光ダイオード (LED) で表示するという独特な方式が採用された。
LEDは寿命保持のため、走行中は消灯する。種別表示は琵琶湖、JR京都・神戸線では「新快速」・「快速」ともに目立ちにくい濃い青色で表記される状態から列車種別により文字色を変える。
塗装
塗装は、「ピュアホワイト」を基本に新快速シンボルカラーである「ブラウン」とJR西日本のコーポレートカラーである「ブルー」によるコンビネーションラインを車体下部に配する。
主要機器
編成や車種構成の都合からMM'ユニット方式と1M方式の2種の主回路構成を採る形式が混在する。機構的には国鉄分割民営化後に製造された205系1000番台(MM'ユニット方式)および213系(1M方式)を基にしており、加えて耐雪ブレーキなどの耐寒・耐雪装備を備える。基本的なシステムは日本国有鉄道(国鉄)時代に新製した211系・213系に準ずるが、高密度高速運転が実施されている線区への導入を前提としていたためもあってか編成内のMT比1:1が維持され、かつ加速度も大きく設定されている。
海からの潮風の影響が考えられるJR京都線・JR神戸線での走行を考慮し、海寄り(1 - 3位側)に空制部品関係、山寄り(2 - 4位側)に電気部品関係を集中的に配置。
電源・制御機器
主制御器は、205系で開発された CS57(MM'ユニット方式)と、213系で開発された CS59(1M方式)をそれぞれ基本とする、WCS57B・WCS59C が搭載されている。制御用引き通しとしてKE96ジャンパ連結器が各車両連結面の2 - 4位寄りに設置されている。
補機用の電源として、213系 (SC22) で実績のあるブースタ方式DC-DCコンバータと3相インバータで構成された静止形インバータ (SIV) WSC23 がクモハ220形・モハ221形・モハ220形に搭載される。集電装置からの直流1,500Vを電源として三相交流440V 60Hz(定格容量130kVA)および 単相交流600V 180Hz(定格容量30kVA)を出力し、三相交流440Vに関しては1 - 3位寄りに設置されたKE5Aジャンパ連結器[* 9]を介して編成に引き通されており、後述する空気圧縮機や冷房装置、室内灯の電源となっている。単相交流600Vに関しては自車搭載の励磁装置の電源である。各車には単巻変圧器が搭載され、三相交流440Vを電源として単相交流100V 60Hzを出力する。これは、各車ヒーターなどの電源として用いられる。SIVが搭載されている車両には補助整流装置も搭載され、三相交流440Vを電源として直流100Vを出力する。モハ221形・クハ220形・サハ220形に搭載される鉛蓄電池 (AB40、容量40Ah) も直流100Vを出力する。
主電動機
713系用として開発された MT61 を基本とする WMT61S(端子電圧375V時定格出力 120 kW)および、213系用として開発された MT64 を基本とする WMT64S(端子電圧750V時定格出力 120 kW)の2種の主電動機がそれぞれ採用。これらは端子電圧は異なるが、磁気回路の工夫などにより出力特性が極力同一となるように設計されており、いずれも全界磁時には既存のMT54系と比較して低定格回転数・強トルクの出力特性を備える。
駆動システムは中空軸平行カルダンである。歯車比は211系と同じ5.19である。
空気供給装置
電動空気圧縮機は、SIV出力の三相交流440V 60Hzを電源とし、低騒音および保守簡易構造である水平対向式4気筒タイプを採用。モハ221形に WMH3093-WTC2000A(吐出し量2,075L/min) が、サハ220形・クハ220形は WMH3094-WTC1000C(吐出し量1,120L/min) が搭載され、信頼性向上のため除湿装置を設ける。
空気圧縮機によって出力された圧縮空気は、自車の元空気ダメに蓄圧される。そして編成に引き通されたMR管を通して各車の供給空気ダメ(ブレーキ系統)や保安空気ダメ(直通予備ブレーキ系統)などに供給される。
集電装置
集電装置は、JR西日本としては初の下枠交差式パンタグラフである WPS27 をクモハ221形、クモハ220形およびモハ220形後位寄りに1基搭載する。
台車
台車には円錐積層ゴムによる軸箱支持機構を備えるボルスタレス台車である DT50・TR235 を基本とする WDT50H(動台車)・WTR235H(付随台車)が採用。台車枠はプレス鋼板製の側梁にシームレスパイプを用いた横梁で構成されたH形形状。横梁内部は空気ばねの補助空気室としている。車体支持装置は、牽引梁を2本の連結器で支持したZリンク式とし、波打一体圧延車輪および両つば式密封円筒ころ軸受を採用。
基礎ブレーキ装置は、WDT50Hが踏面片押しブレーキ、WTR235Hが踏面片押しブレーキと1車軸あたり1枚のディスクブレーキを備える。
細かな差異としては、先頭車両に装着される台車の一部(クモハ221形・クモハ220形の前位側台車およびクハ221形・クハ220形後位側台車)に排障器が取り付けられているほか、モハ220形前位およびサハ220形後位側に装着される台車は側バリ端面が鉛直となっており、排障器の取り付けが可能な設計がされている。
ブレーキ
システムとしては205系や211系などと同様、制御応答性に優れる電力回生併用電気指令式空気ブレーキ方式を採用する。常用ブレーキ、非常ブレーキ、抑速ブレーキ、耐雪ブレーキおよび直通予備ブレーキの5種類を備える。
各車にブレーキ関係の機器(ブレーキ受量器〈クモハ221形・クモハ220形・モハ220形〉、電空変換弁〈電動車〉/多段式中継弁〈付随車〉、増圧電磁弁、応荷重弁など)を一体箱化したブレーキ制御装置を搭載する。電動車では、MM'ユニット方式の場合はクモハ221形に搭載されたブレーキ受量器でユニットを組むモハ221形も含めた2両分を、1M方式の場合はクモハ220形およびモハ220形に搭載され、自車のみの1両分を制御する。ブレーキ受量器で所要ブレーキ力と回生ブレーキ力を演算し、不足するブレーキ力は空気ブレーキで補足するが、ブレーキ受量器からの電気指令を電空変換弁を介して空気指令に変換し、供給空気ダメからブレーキシリンダーに加圧する。付随車では多段式中継弁で運転台からの電気指令を空気指令に変換し、供給空気ダメからブレーキシリンダーに加圧する。
冷房装置
冷房装置は集約分散式の WAU701(冷凍能力18,000kcal/h)2基を各車毎に搭載する。冷房装置 WAU701 に加えて、横流送風機、マイコン式温度調節器、自動巻き取り式フィルタおよび電気暖房機をマイコン制御により全自動運転が可能である。また、車外放送向けに放送用スピーカーを内蔵している[25]。
その他装備
連結器は1編成を1車両として運用する考え方を基本としたため、中間連結部は半永久連結器を使用。先頭車運転台寄りの連結器は117系に倣い、増解結作業の容易化のために、電気連結器・自動解結装置付き密着連結器を採用。
保安装置は、ATS-SとWATS-P。
運転台には映像音声記録装置(ドライブレコーダー)の取り付けが行われている。
警笛は、AW-2およびAW-5が先頭車両床下に搭載されている。
JR221系 奈良〜JR難波.mp3
関西本線(大和路線)で録音をしました。
ーJR西日本221系についてー
車体
車体長は19,670/19,500mm(先頭車/中間車)、車体幅は2,950mm、20m級車体に片側3箇所の両開き扉(開き幅1,300mm)という、近郊形としてはオーソドックスな構成。ただし、113系・115系と比較して両端の側出入口の位置を若干車端に寄せており、制御電動車・制御車の場合は運転台直後に乗降扉が配置される。
車体は普通鋼製である。台枠は、側梁と横梁に一般構造用圧延鋼材 (SS400)、枕梁と中梁に溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 (SMA50B) および高耐候性圧延鋼材 (SPA) を使用した溶接組立構造。側面窓に大型連続窓を採用したことから、腐食防止を考慮して外板には耐候性圧延鋼材 (SPA) を使用し、板厚は側腰板が2.3mm、幕板が1.6mmである。屋根板は、0.6mm厚のステンレス鋼 (SUS) 波板および1.6mm厚の SPA を使用し、ポリウレタン樹脂による塗り屋根としている。床には1.0mm厚のSUS波板を使用する。
床面高さはホームとの段差を小さくするために1,150mm(117系比75mm縮小)とし、屋根高さを46mm上昇、天井機器の小型化により客室高さを
2,330mm(117系比160mm拡大)とした。
種別・行先表示器
車両正面には、列車種別のみを字幕式で表示しているのみで、列車の行先を表示する装置はない。側面の行先表示器は、列車種別を回転式字幕で、行先と号車番号を発光ダイオード (LED) で表示するという独特な方式が採用された。
LEDは寿命保持のため、走行中は消灯する。種別表示は琵琶湖、JR京都・神戸線では「新快速」・「快速」ともに目立ちにくい濃い青色で表記される状態から列車種別により文字色を変える。
塗装
塗装は、「ピュアホワイト」を基本に新快速シンボルカラーである「ブラウン」とJR西日本のコーポレートカラーである「ブルー」によるコンビネーションラインを車体下部に配する。
主要機器
編成や車種構成の都合からMM'ユニット方式と1M方式の2種の主回路構成を採る形式が混在する。機構的には国鉄分割民営化後に製造された205系1000番台(MM'ユニット方式)および213系(1M方式)を基にしており、加えて耐雪ブレーキなどの耐寒・耐雪装備を備える。基本的なシステムは日本国有鉄道(国鉄)時代に新製した211系・213系に準ずるが、高密度高速運転が実施されている線区への導入を前提としていたためもあってか編成内のMT比1:1が維持され、かつ加速度も大きく設定されている。
海からの潮風の影響が考えられるJR京都線・JR神戸線での走行を考慮し、海寄り(1 - 3位側)に空制部品関係、山寄り(2 - 4位側)に電気部品関係を集中的に配置。
電源・制御機器
主制御器は、205系で開発された CS57(MM'ユニット方式)と、213系で開発された CS59(1M方式)をそれぞれ基本とする、WCS57B・WCS59C が搭載されている。制御用引き通しとしてKE96ジャンパ連結器が各車両連結面の2 - 4位寄りに設置されている。
補機用の電源として、213系 (SC22) で実績のあるブースタ方式DC-DCコンバータと3相インバータで構成された静止形インバータ (SIV) WSC23 がクモハ220形・モハ221形・モハ220形に搭載される。集電装置からの直流1,500Vを電源として三相交流440V 60Hz(定格容量130kVA)および 単相交流600V 180Hz(定格容量30kVA)を出力し、三相交流440Vに関しては1 - 3位寄りに設置されたKE5Aジャンパ連結器[* 9]を介して編成に引き通されており、後述する空気圧縮機や冷房装置、室内灯の電源となっている。単相交流600Vに関しては自車搭載の励磁装置の電源である。各車には単巻変圧器が搭載され、三相交流440Vを電源として単相交流100V 60Hzを出力する。これは、各車ヒーターなどの電源として用いられる。SIVが搭載されている車両には補助整流装置も搭載され、三相交流440Vを電源として直流100Vを出力する。モハ221形・クハ220形・サハ220形に搭載される鉛蓄電池 (AB40、容量40Ah) も直流100Vを出力する。
主電動機
713系用として開発された MT61 を基本とする WMT61S(端子電圧375V時定格出力 120 kW)および、213系用として開発された MT64 を基本とする WMT64S(端子電圧750V時定格出力 120 kW)の2種の主電動機がそれぞれ採用。これらは端子電圧は異なるが、磁気回路の工夫などにより出力特性が極力同一となるように設計されており、いずれも全界磁時には既存のMT54系と比較して低定格回転数・強トルクの出力特性を備える。
駆動システムは中空軸平行カルダンである。歯車比は211系と同じ5.19である。
空気供給装置
電動空気圧縮機は、SIV出力の三相交流440V 60Hzを電源とし、低騒音および保守簡易構造である水平対向式4気筒タイプを採用。モハ221形に WMH3093-WTC2000A(吐出し量2,075L/min) が、サハ220形・クハ220形は WMH3094-WTC1000C(吐出し量1,120L/min) が搭載され、信頼性向上のため除湿装置を設ける。
空気圧縮機によって出力された圧縮空気は、自車の元空気ダメに蓄圧される。そして編成に引き通されたMR管を通して各車の供給空気ダメ(ブレーキ系統)や保安空気ダメ(直通予備ブレーキ系統)などに供給される。
集電装置
集電装置は、JR西日本としては初の下枠交差式パンタグラフである WPS27 をクモハ221形、クモハ220形およびモハ220形後位寄りに1基搭載する。
台車
台車には円錐積層ゴムによる軸箱支持機構を備えるボルスタレス台車である DT50・TR235 を基本とする WDT50H(動台車)・WTR235H(付随台車)が採用。台車枠はプレス鋼板製の側梁にシームレスパイプを用いた横梁で構成されたH形形状。横梁内部は空気ばねの補助空気室としている。車体支持装置は、牽引梁を2本の連結器で支持したZリンク式とし、波打一体圧延車輪および両つば式密封円筒ころ軸受を採用。
基礎ブレーキ装置は、WDT50Hが踏面片押しブレーキ、WTR235Hが踏面片押しブレーキと1車軸あたり1枚のディスクブレーキを備える。
細かな差異としては、先頭車両に装着される台車の一部(クモハ221形・クモハ220形の前位側台車およびクハ221形・クハ220形後位側台車)に排障器が取り付けられているほか、モハ220形前位およびサハ220形後位側に装着される台車は側バリ端面が鉛直となっており、排障器の取り付けが可能な設計がされている。
ブレーキ
システムとしては205系や211系などと同様、制御応答性に優れる電力回生併用電気指令式空気ブレーキ方式を採用する。常用ブレーキ、非常ブレーキ、抑速ブレーキ、耐雪ブレーキおよび直通予備ブレーキの5種類を備える。
各車にブレーキ関係の機器(ブレーキ受量器〈クモハ221形・クモハ220形・モハ220形〉、電空変換弁〈電動車〉/多段式中継弁〈付随車〉、増圧電磁弁、応荷重弁など)を一体箱化したブレーキ制御装置を搭載する。電動車では、MM'ユニット方式の場合はクモハ221形に搭載されたブレーキ受量器でユニットを組むモハ221形も含めた2両分を、1M方式の場合はクモハ220形およびモハ220形に搭載され、自車のみの1両分を制御する。ブレーキ受量器で所要ブレーキ力と回生ブレーキ力を演算し、不足するブレーキ力は空気ブレーキで補足するが、ブレーキ受量器からの電気指令を電空変換弁を介して空気指令に変換し、供給空気ダメからブレーキシリンダーに加圧する。付随車では多段式中継弁で運転台からの電気指令を空気指令に変換し、供給空気ダメからブレーキシリンダーに加圧する。
冷房装置
冷房装置は集約分散式の WAU701(冷凍能力18,000kcal/h)2基を各車毎に搭載する。冷房装置 WAU701 に加えて、横流送風機、マイコン式温度調節器、自動巻き取り式フィルタおよび電気暖房機をマイコン制御により全自動運転が可能である。また、車外放送向けに放送用スピーカーを内蔵している[25]。
その他装備
連結器は1編成を1車両として運用する考え方を基本としたため、中間連結部は半永久連結器を使用。先頭車運転台寄りの連結器は117系に倣い、増解結作業の容易化のために、電気連結器・自動解結装置付き密着連結器を採用。
保安装置は、ATS-SとWATS-P。
運転台には映像音声記録装置(ドライブレコーダー)の取り付けが行われている。
警笛は、AW-2およびAW-5が先頭車両床下に搭載されている。
 JR207系 京橋〜宝塚.mp3
JR東西線、宝塚線の区間で録音しました。JR東西線は地下で京橋から尼崎を結ぶ。
〜JR207系について〜
JRの通勤形電車としては標準的な、片側4箇所に客用ドアを設けた20m車体で、構体の材質は1988年に阪和線用として投入された205系1000番台に続いてビード加工軽量オールステンレス構体で前頭部の前面は普通鋼製、側面および屋根面は FRP 製となっている。在来の通勤形電車が車体幅2,800mmだったのに対し、本系列は定員増を狙った近郊形電車に見られるような2,950mmのワイドボディが国鉄・JRで初めて採用された点が特徴。
妻面には、妻壁外面に設置された消火器を車内に取り込む経路として、また非常時の換気用の開口面積を確保する目的で大型の一枚下降窓が備わっている。このため、車両間同士を繋ぐ客用貫通路が中央からJR神戸線走行時で北寄りにオフセット設置されており、左右非対称になっている。また、妻面壁の上部に通気孔が設けられている。
転落防止幌は2002年の2000番台の1次製造分から装備されており、2006年より1000番台のS18編成を除いた全編成に設置された。
種別・行き先表示器
種別・行先表示器は221系で採用した方式と同じ回転幕式と発光ダイオード (LED) 式との併用。回転幕は列車の種別・線区、LED は行き先を表示している。
主要機器
JR西日本初のVVVF制御装置搭載形式。製造期間が約10年の長期にわたっているため、製造時期により、例えばVVVFインバータの制御素子はゲートターンオフサイリスタ (GTO) 、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ (IGBT) などの差異がある。
パンタグラフは下枠交差式の WPS27 形をクモハ207形およびモハ207形1両あたり2基搭載する。JR東西線以外では第1パンタグラフのみを上げて走行し、尼崎駅と京橋駅で第2パンタグラフの昇降を行っている。
駆動装置は国鉄・JRを通して在来線電車としては初のWNドライブが採用された。
屋根上機器は221系を踏襲した集約分散式冷房装置2基を全車に搭載している。
運転設備
運転台のマスコンは1989年の221系の設計を受け継いだ横軸ツインレバー型。力行ノッチ6段、常用ブレーキ8段は、後継の321系と共にJR西日本の電車として最大である。2000番台と体質改善車をのぞき、圧力計などの各計器類はデジタル表示となっている。運転台右横に設置された液晶モニタ装置では、車両の様々な状態を一度に監視したり、空調等の各設定を行うことが可能で、運転・車掌業務をサポートしている。
JR207系 京橋〜宝塚.mp3
JR東西線、宝塚線の区間で録音しました。JR東西線は地下で京橋から尼崎を結ぶ。
〜JR207系について〜
JRの通勤形電車としては標準的な、片側4箇所に客用ドアを設けた20m車体で、構体の材質は1988年に阪和線用として投入された205系1000番台に続いてビード加工軽量オールステンレス構体で前頭部の前面は普通鋼製、側面および屋根面は FRP 製となっている。在来の通勤形電車が車体幅2,800mmだったのに対し、本系列は定員増を狙った近郊形電車に見られるような2,950mmのワイドボディが国鉄・JRで初めて採用された点が特徴。
妻面には、妻壁外面に設置された消火器を車内に取り込む経路として、また非常時の換気用の開口面積を確保する目的で大型の一枚下降窓が備わっている。このため、車両間同士を繋ぐ客用貫通路が中央からJR神戸線走行時で北寄りにオフセット設置されており、左右非対称になっている。また、妻面壁の上部に通気孔が設けられている。
転落防止幌は2002年の2000番台の1次製造分から装備されており、2006年より1000番台のS18編成を除いた全編成に設置された。
種別・行き先表示器
種別・行先表示器は221系で採用した方式と同じ回転幕式と発光ダイオード (LED) 式との併用。回転幕は列車の種別・線区、LED は行き先を表示している。
主要機器
JR西日本初のVVVF制御装置搭載形式。製造期間が約10年の長期にわたっているため、製造時期により、例えばVVVFインバータの制御素子はゲートターンオフサイリスタ (GTO) 、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ (IGBT) などの差異がある。
パンタグラフは下枠交差式の WPS27 形をクモハ207形およびモハ207形1両あたり2基搭載する。JR東西線以外では第1パンタグラフのみを上げて走行し、尼崎駅と京橋駅で第2パンタグラフの昇降を行っている。
駆動装置は国鉄・JRを通して在来線電車としては初のWNドライブが採用された。
屋根上機器は221系を踏襲した集約分散式冷房装置2基を全車に搭載している。
運転設備
運転台のマスコンは1989年の221系の設計を受け継いだ横軸ツインレバー型。力行ノッチ6段、常用ブレーキ8段は、後継の321系と共にJR西日本の電車として最大である。2000番台と体質改善車をのぞき、圧力計などの各計器類はデジタル表示となっている。運転台右横に設置された液晶モニタ装置では、車両の様々な状態を一度に監視したり、空調等の各設定を行うことが可能で、運転・車掌業務をサポートしている。 JR323系 桃谷〜桃谷.mp3
朝早くに乗車して録音しましたが、そこそこ乗客がおり、少し声が聞こえます。
〜JR西日本323系について〜
車体
車体長は19,570/19,500mm(先頭車/中間車)、車体幅は2,950mm、20m級車体に片側3箇所の両開き扉という、通勤形でありながら近郊形と同様のドア配置としている。これは大阪環状線への将来的なホームドア導入に向けて221系・223系・225系などとドア配置を共通化させるとともに、連結面-車端出入り口寸法を先頭車・中間車で共通化させている。材質はステンレス鋼 (SUS301, SUS304) を基本とし、運転台部分のみ高耐候性圧延鋼材 (SPA) が用いられている。外板厚は、妻面が1.5mm、側面が2mm、運転台が4.5mmとなっている。全電動車編成とすることによって、車両構体の共通化によるコスト削減が図られている。安全対策として、前面衝撃吸収構造の採用のほか、側面衝突やオフセット衝突対策が実施されている。
前頭部形状および標識灯配置は521系3次車や225系2次車、227系と同じとし、省エネ・長寿命化の観点から、前部標識灯(前照灯)およびフォグランプはHIDからLEDに変更。標識灯配色はアンバーと白の組み合わせであり、従来車からの変化はない。ストライプやドア横のアクセントカラーとして、103系や201系の車体色に用いられた大阪環状線伝統の朱色1号(オレンジバーミリオン)が配され、大阪環状線改造プロジェクトのロゴマークが先頭部および側面にデザインされているほか、ドアの位置や動作状況が分かるようにドア上部に大阪環状線改造プロジェクトのロゴマークにちなんだ標記とドア先端に黄色のラインを配置している。4号車は終日女性専用車両として使用されるため、ドア横に女性専用車の標記とともにアクセントカラーをピンク色としている。
側窓はグリーン系の熱線吸収複層合わせガラスを採用し、225系と同様のレイアウトで側扉間は3枚構成、車端は1枚構成である。側扉間の3枚は、側扉側の2枚は降下窓、中央部は大型の1枚の固定窓となっている。乗務員室の前面窓は、グリーン系の電熱線入りの3次曲面で構成された熱線吸収合わせ磨きガラスとしている。
主要機器
321系や225系などで採用された、1車両中に動力台車と付随台車を1台ずつ配置し運転に必要な機器類を1両にまとめて搭載する「0.5Mシステム」と呼ばれる考え方を基本とし、すべての車両が電動車となっている。そのため、全車両に車両制御装置を搭載することを基本とし、クモハ323形・モハ323形には集電装置および空気圧縮機を装備している。
221系以降の設計思想を引き継ぎ、1 - 3位側(海側)に空制部品関係を、2 - 4位側(山側)に電気部品関係を集中的に配置。
電源・制御機器
車両制御装置はWPC16。主電動機を制御する主回路部と補機類の電源となる補助電源部(補助電源装置)が一体箱化したユニットである。主回路部はSiC適用のMOSFET素子を使用した2レベル電圧形PWMインバータで、インバータ1基で2基の主電動機を制御する1C2M構成のVVVFインバータを搭載。補助電源部はIGBT素子を使用した2レベル電圧形PWMインバータで三相交流440V、75kVAの容量を有しており、インバータをCVCF制御し、他車の車両制御装置の補助電源部と並列運転を行うことで故障時の編成全体での冗長性を確保する設計となっている。
集電装置はシングルアーム型パンタグラフWPS28Eを採用し、クモハ323形・モハ323形後位寄りに加え、モハ323形0番台前位寄りにも予備パンタグラフとして搭載する。バネ上昇式・空気下降式であり、大容量集電カーボンすり板、上昇検知装置および電磁カギ外し装置を備える。
主電動機は全閉式かご形三相誘導電動機 WMT107 が採用され、各車両に2基搭載。1時間定格出力は220kW以上である[15]。全閉式とすることで車内静穏化を図るとともに、非分解での軸受交換を可能とすることでメンテナンス性が向上している。
空調装置は、新鮮外気導入機能を備えた集約分散式の WAU708B を屋根上に1両あたり2台搭載しており、容量は 20,000 kcal/h 以上である。
車両異常挙動検知システムを装備しており、連結器脇に車両挙動監視装置を1両あたり2基、車両制御装置の脇には車両挙動表示灯箱が1両あたり2基搭載。
空気供給装置
電動空気圧縮機は、除湿装置と一体化した低騒音型スクリュー式 WMH3098A-WRC1600 をクモハ323形・モハ323形0番台に搭載。
各車両には、電動空気圧縮機から供給された空気を貯蔵する元空気タンクとドアの開閉などで用いる制御空気タンクを一体化した二室空気タンクが車両中央付近に1基、常用・非常ブレーキで用いる供給空気タンクが台車近傍の山側に2基搭載されている。
台車
台車は、225系や321系、227系などで実績のある軸箱支持装置が軸梁式のボルスタレス台車である。奇数形式(クモハ323形・モハ323形)の場合は前位寄りに付随台車、後位寄りに電動台車を装着している。偶数形式(クモハ322形・モハ322形)の場合はその逆である。
電動台車は WDT63C で、基礎ブレーキは踏面片押しユニットブレーキである。付随台車は中間車(モハ323形・モハ322形)が WTR246H 、先頭車(クモハ323形・クモハ322形)が WTR246I で、基礎ブレーキは踏面片押しユニットブレーキ+1軸2枚のディスクブレーキである。加えて、WTR246I にはバネ式駐車ブレーキが備えられている。
運転台
運転台計器盤は計器類と表示灯を廃し、タッチパネルの液晶モニターに表示するグラスコックピット構造の計器盤設定器を運転台正面に2台と右側そで部に1台を採用。JR西日本の在来線車両では227系についで2例目である。主幹制御器は、221系以来実績のあるブレーキとマスコンが別々の横軸ツインレバー型としている。
その他装備
連結器は1編成を1車両として運用する考え方を基本としたため、中間連結部は半永久連結器を使用することを基本としている。検修の都合上、3両と5両に分割できるようにするためにモハ322形(6号車)後位およびモハ323形500番台(5号車)前位は密着連結器としている。先頭車運転台寄りの連結器も密着連結器としているが、営業列車での増解結作業が存在しないことから、電気連結器・自動解結装置は搭載しない。すべての連結器にばね式胴受けと元空気ダメ間引き通しを備えている。
保安装置は、新製当初からATS-SWおよびATS-Pのほか、EB・TE装置、映像音声記録装置に加えてEB-N装置が新たに搭載される。警笛は、AW-2、AW-5およびミュージックホーンが先頭車両床下に搭載される。
先頭車の運転台寄り(クモハ323形前位寄りおよびクモハ322形後位寄り)の下部にはドア誤扱い防止対策用のホーム検知センサーが取り付けられている。
JR323系 桃谷〜桃谷.mp3
朝早くに乗車して録音しましたが、そこそこ乗客がおり、少し声が聞こえます。
〜JR西日本323系について〜
車体
車体長は19,570/19,500mm(先頭車/中間車)、車体幅は2,950mm、20m級車体に片側3箇所の両開き扉という、通勤形でありながら近郊形と同様のドア配置としている。これは大阪環状線への将来的なホームドア導入に向けて221系・223系・225系などとドア配置を共通化させるとともに、連結面-車端出入り口寸法を先頭車・中間車で共通化させている。材質はステンレス鋼 (SUS301, SUS304) を基本とし、運転台部分のみ高耐候性圧延鋼材 (SPA) が用いられている。外板厚は、妻面が1.5mm、側面が2mm、運転台が4.5mmとなっている。全電動車編成とすることによって、車両構体の共通化によるコスト削減が図られている。安全対策として、前面衝撃吸収構造の採用のほか、側面衝突やオフセット衝突対策が実施されている。
前頭部形状および標識灯配置は521系3次車や225系2次車、227系と同じとし、省エネ・長寿命化の観点から、前部標識灯(前照灯)およびフォグランプはHIDからLEDに変更。標識灯配色はアンバーと白の組み合わせであり、従来車からの変化はない。ストライプやドア横のアクセントカラーとして、103系や201系の車体色に用いられた大阪環状線伝統の朱色1号(オレンジバーミリオン)が配され、大阪環状線改造プロジェクトのロゴマークが先頭部および側面にデザインされているほか、ドアの位置や動作状況が分かるようにドア上部に大阪環状線改造プロジェクトのロゴマークにちなんだ標記とドア先端に黄色のラインを配置している。4号車は終日女性専用車両として使用されるため、ドア横に女性専用車の標記とともにアクセントカラーをピンク色としている。
側窓はグリーン系の熱線吸収複層合わせガラスを採用し、225系と同様のレイアウトで側扉間は3枚構成、車端は1枚構成である。側扉間の3枚は、側扉側の2枚は降下窓、中央部は大型の1枚の固定窓となっている。乗務員室の前面窓は、グリーン系の電熱線入りの3次曲面で構成された熱線吸収合わせ磨きガラスとしている。
主要機器
321系や225系などで採用された、1車両中に動力台車と付随台車を1台ずつ配置し運転に必要な機器類を1両にまとめて搭載する「0.5Mシステム」と呼ばれる考え方を基本とし、すべての車両が電動車となっている。そのため、全車両に車両制御装置を搭載することを基本とし、クモハ323形・モハ323形には集電装置および空気圧縮機を装備している。
221系以降の設計思想を引き継ぎ、1 - 3位側(海側)に空制部品関係を、2 - 4位側(山側)に電気部品関係を集中的に配置。
電源・制御機器
車両制御装置はWPC16。主電動機を制御する主回路部と補機類の電源となる補助電源部(補助電源装置)が一体箱化したユニットである。主回路部はSiC適用のMOSFET素子を使用した2レベル電圧形PWMインバータで、インバータ1基で2基の主電動機を制御する1C2M構成のVVVFインバータを搭載。補助電源部はIGBT素子を使用した2レベル電圧形PWMインバータで三相交流440V、75kVAの容量を有しており、インバータをCVCF制御し、他車の車両制御装置の補助電源部と並列運転を行うことで故障時の編成全体での冗長性を確保する設計となっている。
集電装置はシングルアーム型パンタグラフWPS28Eを採用し、クモハ323形・モハ323形後位寄りに加え、モハ323形0番台前位寄りにも予備パンタグラフとして搭載する。バネ上昇式・空気下降式であり、大容量集電カーボンすり板、上昇検知装置および電磁カギ外し装置を備える。
主電動機は全閉式かご形三相誘導電動機 WMT107 が採用され、各車両に2基搭載。1時間定格出力は220kW以上である[15]。全閉式とすることで車内静穏化を図るとともに、非分解での軸受交換を可能とすることでメンテナンス性が向上している。
空調装置は、新鮮外気導入機能を備えた集約分散式の WAU708B を屋根上に1両あたり2台搭載しており、容量は 20,000 kcal/h 以上である。
車両異常挙動検知システムを装備しており、連結器脇に車両挙動監視装置を1両あたり2基、車両制御装置の脇には車両挙動表示灯箱が1両あたり2基搭載。
空気供給装置
電動空気圧縮機は、除湿装置と一体化した低騒音型スクリュー式 WMH3098A-WRC1600 をクモハ323形・モハ323形0番台に搭載。
各車両には、電動空気圧縮機から供給された空気を貯蔵する元空気タンクとドアの開閉などで用いる制御空気タンクを一体化した二室空気タンクが車両中央付近に1基、常用・非常ブレーキで用いる供給空気タンクが台車近傍の山側に2基搭載されている。
台車
台車は、225系や321系、227系などで実績のある軸箱支持装置が軸梁式のボルスタレス台車である。奇数形式(クモハ323形・モハ323形)の場合は前位寄りに付随台車、後位寄りに電動台車を装着している。偶数形式(クモハ322形・モハ322形)の場合はその逆である。
電動台車は WDT63C で、基礎ブレーキは踏面片押しユニットブレーキである。付随台車は中間車(モハ323形・モハ322形)が WTR246H 、先頭車(クモハ323形・クモハ322形)が WTR246I で、基礎ブレーキは踏面片押しユニットブレーキ+1軸2枚のディスクブレーキである。加えて、WTR246I にはバネ式駐車ブレーキが備えられている。
運転台
運転台計器盤は計器類と表示灯を廃し、タッチパネルの液晶モニターに表示するグラスコックピット構造の計器盤設定器を運転台正面に2台と右側そで部に1台を採用。JR西日本の在来線車両では227系についで2例目である。主幹制御器は、221系以来実績のあるブレーキとマスコンが別々の横軸ツインレバー型としている。
その他装備
連結器は1編成を1車両として運用する考え方を基本としたため、中間連結部は半永久連結器を使用することを基本としている。検修の都合上、3両と5両に分割できるようにするためにモハ322形(6号車)後位およびモハ323形500番台(5号車)前位は密着連結器としている。先頭車運転台寄りの連結器も密着連結器としているが、営業列車での増解結作業が存在しないことから、電気連結器・自動解結装置は搭載しない。すべての連結器にばね式胴受けと元空気ダメ間引き通しを備えている。
保安装置は、新製当初からATS-SWおよびATS-Pのほか、EB・TE装置、映像音声記録装置に加えてEB-N装置が新たに搭載される。警笛は、AW-2、AW-5およびミュージックホーンが先頭車両床下に搭載される。
先頭車の運転台寄り(クモハ323形前位寄りおよびクモハ322形後位寄り)の下部にはドア誤扱い防止対策用のホーム検知センサーが取り付けられている。
 JR201系 桃谷〜桃谷.mp3
東日本からは引退してしまいましたが、西日本では車両数は少なくなりましたが現役で運行されています。大阪環状線ではオレンジの編成とユニバーサルスタジオジャパン(USJ)のラッピング編成がいます。大阪環状線の一部は桜島線への直通があります。
〜JR201系について〜
車体
外板腐食対策として、雨樋と外板の一体化による屋根の張上化・戸袋窓の埋め込みが行われており、ドア間窓を下段:固定・上段:2分割上昇の3分割バス風逆T字サッシに交換されている。運転台周りに関しては、窓周囲の材質をステンレスに、前照灯はガラス内収納式となっている。
電源・制御機器
MM'ユニットを採用し、M車(モハ201形)にはチョッパ制御器・主制御器・抵抗器・集電装置が、M'車(クモハ200形・モハ200形)には補助電源装置・電動空気圧縮機が搭載。
主回路にCH1系電機子チョッパ制御器もしくはCS53系主制御器を組み合わせて搭載し、これらによってMT60形主電動機(直巻整流子電動機)を制御する。
補助電源装置にはブラシレスMG DM106(定格容量190kVA)を、空気圧縮機 (CP) にはメンテナンスフリー化を図って誘導電動機を採用したレシプロ式 MH3075A-C2000M を使用する。
運転台の主幹制御器は、横軸式ハンドルの MC60 、ブレーキ弁は通常のME49形を搭載。
ブレーキ
応荷重装置付き電機子チョッパ制御回生ブレーキ併用電磁直通空気ブレーキ(SELR)と自動ブレーキ部のブレーキ制御弁として3圧力式のE制御弁が採用されている。
台車
DT46B(動力台車)
TR231A(付随台車)
JR201系 桃谷〜桃谷.mp3
東日本からは引退してしまいましたが、西日本では車両数は少なくなりましたが現役で運行されています。大阪環状線ではオレンジの編成とユニバーサルスタジオジャパン(USJ)のラッピング編成がいます。大阪環状線の一部は桜島線への直通があります。
〜JR201系について〜
車体
外板腐食対策として、雨樋と外板の一体化による屋根の張上化・戸袋窓の埋め込みが行われており、ドア間窓を下段:固定・上段:2分割上昇の3分割バス風逆T字サッシに交換されている。運転台周りに関しては、窓周囲の材質をステンレスに、前照灯はガラス内収納式となっている。
電源・制御機器
MM'ユニットを採用し、M車(モハ201形)にはチョッパ制御器・主制御器・抵抗器・集電装置が、M'車(クモハ200形・モハ200形)には補助電源装置・電動空気圧縮機が搭載。
主回路にCH1系電機子チョッパ制御器もしくはCS53系主制御器を組み合わせて搭載し、これらによってMT60形主電動機(直巻整流子電動機)を制御する。
補助電源装置にはブラシレスMG DM106(定格容量190kVA)を、空気圧縮機 (CP) にはメンテナンスフリー化を図って誘導電動機を採用したレシプロ式 MH3075A-C2000M を使用する。
運転台の主幹制御器は、横軸式ハンドルの MC60 、ブレーキ弁は通常のME49形を搭載。
ブレーキ
応荷重装置付き電機子チョッパ制御回生ブレーキ併用電磁直通空気ブレーキ(SELR)と自動ブレーキ部のブレーキ制御弁として3圧力式のE制御弁が採用されている。
台車
DT46B(動力台車)
TR231A(付随台車) 秩父鉄道7700系 羽生〜熊谷.mp3
秩父鉄道本線 羽生→熊谷の区間で録音。秩父鉄道は全区間を走る列車は少なく、三峰口→熊谷と熊谷→羽生と分かれた運用が多くなっている。
秩父鉄道7700系は東急から譲渡の車両で、東急では東横線、大井町線で活躍していました。
~秩父鉄道7500系について~
老朽化した1000系(元国鉄101系)の置き換えのため、東急大井町線で使用されていた東急8090系5両編成のうち、3両を譲り受け、秩父鉄道で運用するに当たって改造を行い、羽生方からT1c(制御)- M1(電動車) - M2c(制御電動車)の3両編成にしたものである。
車体
三峰口方先頭車のデハ7500形(元クハ8090形)は電動車に改造された。中間車のデハ7600形(元デハ8190形)は、パンタグラフがシングルアーム型から従来の菱型に戻されたほか、増設も行われている。なお、それにともないパンタグラフの設置場所を確保するために冷房装置を1基撤去している。前面の帯は先に導入された7000系(元東急8500系)と同じ緑色→黄色のグラデーションに張替えられたほか、側面の帯も緑色に変更された。
主制御装置、台車など
台車 ペデスタル+軸バネ方式空気バネ台車 TS-807形・ TS-815形
主電動機 直流複巻電動機 TKM-80形
駆動方式 中空軸平行カルダン駆動方式
制御装置 界磁チョッパ制御
制動装置 回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ
保安装置 秩父鉄道形ATS装置
車内
車椅子スペース、ドアチャイムとドア開閉表示灯、客用扉用の開閉ボタン、LED式車内案内表示器の設置、貫通路開き戸の追加(デハ7600形のみ)などの改造が行われている。
秩父鉄道7700系 羽生〜熊谷.mp3
秩父鉄道本線 羽生→熊谷の区間で録音。秩父鉄道は全区間を走る列車は少なく、三峰口→熊谷と熊谷→羽生と分かれた運用が多くなっている。
秩父鉄道7700系は東急から譲渡の車両で、東急では東横線、大井町線で活躍していました。
~秩父鉄道7500系について~
老朽化した1000系(元国鉄101系)の置き換えのため、東急大井町線で使用されていた東急8090系5両編成のうち、3両を譲り受け、秩父鉄道で運用するに当たって改造を行い、羽生方からT1c(制御)- M1(電動車) - M2c(制御電動車)の3両編成にしたものである。
車体
三峰口方先頭車のデハ7500形(元クハ8090形)は電動車に改造された。中間車のデハ7600形(元デハ8190形)は、パンタグラフがシングルアーム型から従来の菱型に戻されたほか、増設も行われている。なお、それにともないパンタグラフの設置場所を確保するために冷房装置を1基撤去している。前面の帯は先に導入された7000系(元東急8500系)と同じ緑色→黄色のグラデーションに張替えられたほか、側面の帯も緑色に変更された。
主制御装置、台車など
台車 ペデスタル+軸バネ方式空気バネ台車 TS-807形・ TS-815形
主電動機 直流複巻電動機 TKM-80形
駆動方式 中空軸平行カルダン駆動方式
制御装置 界磁チョッパ制御
制動装置 回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ
保安装置 秩父鉄道形ATS装置
車内
車椅子スペース、ドアチャイムとドア開閉表示灯、客用扉用の開閉ボタン、LED式車内案内表示器の設置、貫通路開き戸の追加(デハ7600形のみ)などの改造が行われている。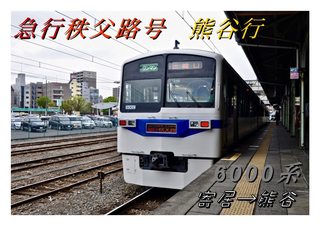 秩父鉄道6000系 寄居〜熊谷.mp3
6000系で運転されている急行を録音。
〜秩父鉄道6000系について〜
2006の11月に引退した3000系に変わる秩父鉄道の急行型車両。
カラーは先代の 3000系の白と青(水色)の少し流線美を持たせながらのツートンカラー。
種車は、相互直通を行う西武鉄道、新101系 ですが、かなり前面改造・内装改造が施されている。
西武20000系増備により余剰となった西武新101系が譲渡された後、秩父鉄道広瀬川原工場で改造。
通勤型である西武新101系の状態では、秩父鉄道を走る他の形式とサービス面で変わらない為、内装はクロスシートに改造。
座席はニューレッドアロー(NRA)の旧座席です。リクライニング機能は残したものの転換はしない固定の仕様になっている。
西武新101系は3ドア車両でしたが、先代の3000系の伝統に習い、2ドアに改造。
機器類はパンタグラフなどにはほとんど手を加えていない為、前面改造工事と内装工事が主として行われた形式。
先代の3000系(元国鉄165系)は車掌乗務によるツーマン運転でしたが、6000系からは急行列車もワンマン運転となりました。
秩父鉄道6000系 寄居〜熊谷.mp3
6000系で運転されている急行を録音。
〜秩父鉄道6000系について〜
2006の11月に引退した3000系に変わる秩父鉄道の急行型車両。
カラーは先代の 3000系の白と青(水色)の少し流線美を持たせながらのツートンカラー。
種車は、相互直通を行う西武鉄道、新101系 ですが、かなり前面改造・内装改造が施されている。
西武20000系増備により余剰となった西武新101系が譲渡された後、秩父鉄道広瀬川原工場で改造。
通勤型である西武新101系の状態では、秩父鉄道を走る他の形式とサービス面で変わらない為、内装はクロスシートに改造。
座席はニューレッドアロー(NRA)の旧座席です。リクライニング機能は残したものの転換はしない固定の仕様になっている。
西武新101系は3ドア車両でしたが、先代の3000系の伝統に習い、2ドアに改造。
機器類はパンタグラフなどにはほとんど手を加えていない為、前面改造工事と内装工事が主として行われた形式。
先代の3000系(元国鉄165系)は車掌乗務によるツーマン運転でしたが、6000系からは急行列車もワンマン運転となりました。 JR209系 秋葉原〜新宿.m4a録音の日は東京ドームでコンサートがあり、水道橋駅が混雑し、停車時間が変更されていました。
〜JR209系について〜中央・総武緩行線の103系を置き換えるために1998年(平成10年)11月に落成し、同年12月29日から営業運転を開始。このグループはJR東日本新津車両製作所が初めて独自に設計から製造までを行った車両である(全車両が新津車両製作所製)。
車体車体は209系950番台をベースとした 2950mm の拡幅車体(従来車より150mm拡大)とされている。従来車では先頭車の車体長が中間車に比べて420mm 長かったが、本番台区分では中間車と同じ19500mm(全長20000mm)に揃えられた。その関係で先頭車の第1ドア・第2ドア間の寸法が短くなり、従来車ではすべて7人掛けであったドア間の座席がこの部分のみ6人掛けとなっている。台車中心間隔は拡幅車体の採用による曲線での偏倚量の関係(拡幅車体で台車中心間距離を13300mmにした場合、曲線通過時に車体のはみ出しが多すぎてしまう)で、同じ拡幅車体のE217系などと同様に13800mmとなっている。なお、500番台という番台区分はこの車体形状の変更に由来する。基本的に車内は0番台を基本としており、座席は片持ち式のバケットシートである 。このうち、座席クッション材はウレタンからポリエステル樹脂成形品を使用することで汚損時の表皮張り替えを容易にしたほか、合わせて廃棄時のリサイクル性も高められている。車内非常通報装置は警報式から乗務員と相互に通話が可能な通話式へと変更。側面のドア間の大窓は従来車がすべて固定式であったのに対し、本番台区分では第1ドア・第2ドア間(先頭車を除く)と第3ドア・第4ドア間にある大窓(1両あたり4か所(先頭車は2か所))の車端寄り3分の2が開閉可能な下降窓構造に変更。行先表示器と運行番号表示器は字幕式をやめ、LED方式を採用。
制御装置など制御装置をはじめとした走行機器類は0番台と同様。台車はヨーダンパ取り付け台座付きである(M、M'車:DT61形、T、T'車:TR246形)。
パンタグラフは電磁鉤外し機能付きのPS28B形菱形を使用している。
JR209系 秋葉原〜新宿.m4a録音の日は東京ドームでコンサートがあり、水道橋駅が混雑し、停車時間が変更されていました。
〜JR209系について〜中央・総武緩行線の103系を置き換えるために1998年(平成10年)11月に落成し、同年12月29日から営業運転を開始。このグループはJR東日本新津車両製作所が初めて独自に設計から製造までを行った車両である(全車両が新津車両製作所製)。
車体車体は209系950番台をベースとした 2950mm の拡幅車体(従来車より150mm拡大)とされている。従来車では先頭車の車体長が中間車に比べて420mm 長かったが、本番台区分では中間車と同じ19500mm(全長20000mm)に揃えられた。その関係で先頭車の第1ドア・第2ドア間の寸法が短くなり、従来車ではすべて7人掛けであったドア間の座席がこの部分のみ6人掛けとなっている。台車中心間隔は拡幅車体の採用による曲線での偏倚量の関係(拡幅車体で台車中心間距離を13300mmにした場合、曲線通過時に車体のはみ出しが多すぎてしまう)で、同じ拡幅車体のE217系などと同様に13800mmとなっている。なお、500番台という番台区分はこの車体形状の変更に由来する。基本的に車内は0番台を基本としており、座席は片持ち式のバケットシートである 。このうち、座席クッション材はウレタンからポリエステル樹脂成形品を使用することで汚損時の表皮張り替えを容易にしたほか、合わせて廃棄時のリサイクル性も高められている。車内非常通報装置は警報式から乗務員と相互に通話が可能な通話式へと変更。側面のドア間の大窓は従来車がすべて固定式であったのに対し、本番台区分では第1ドア・第2ドア間(先頭車を除く)と第3ドア・第4ドア間にある大窓(1両あたり4か所(先頭車は2か所))の車端寄り3分の2が開閉可能な下降窓構造に変更。行先表示器と運行番号表示器は字幕式をやめ、LED方式を採用。
制御装置など制御装置をはじめとした走行機器類は0番台と同様。台車はヨーダンパ取り付け台座付きである(M、M'車:DT61形、T、T'車:TR246形)。
パンタグラフは電磁鉤外し機能付きのPS28B形菱形を使用している。 JR209系 千葉〜佐倉.m4a
総武本線の運用を録音。
〜JR209系について〜
千葉支社管内で運用されていた113系・211系置き換え用に導入された車両で、10両編成を組成していた0番台を4両編成または6両編成に組成変更されたものである。帯色は同支社管内の211系に準じた黄色と青色の房総色である。
ドアエンジン方式の差異から、空気式ドアエンジン装備車(種車が0番台1・2次車)は2000番台、電気式ドアエンジン装備車(種車が0番台3次車以降)は2100番台に区分されている。
6両編成の車両については、元々の10両編成からサハ4両が単純に取り除かれたものであるが、4両編成については他の編成の先頭車と電動車(中間車)から再組成したものも存在する。そのため、4両編成の先頭車の一部には2000番台の空気式ドアエンジン車両と川崎重工業製車両(空気式・電気式の両方)が含まれる。なお川崎重工業製の中間車は車体構造の都合で転用対象外となっている。
車体
外観では行先表示器のLED化、排障器(スカート)を強化型へ交換、併結運転のため、全ての先頭車に電気連結器と自動解結装置が搭載されている。また、2000番台の先頭車には蓄電池と整流装置 (ARf) が搭載されていなかったため、廃車となったモハ208形から流用。
車内は先頭車両の客用ドア間の座席をセミクロスシートへ改造、「ドア3/4閉スイッチ」の設置、2号車に組成されるモハ208形への車椅子対応の大形トイレ(真空式)設置も行われ、設置に伴い窓が埋められ、床下には汚物処理装置も搭載された。
車内非常通報装置は警報式から乗務員と相互に通話が可能な通話式へと変更。
制御装置など
主要機器は転用改造に合わせてE217系と同じ機器への更新工事を実施している。更新内容としてはVVVFインバータ装置と補助電源装置(静止形インバータ)は、制御素子としてGTOサイリスタを用いたものからIGBTを用いた SC88A および SC92 に、制御伝送装置は MON19 に変更。さらに、ブレーキ制御装置や戸閉制御装置など主要機器についても更新され、ATS-P装置や補助電源装置に関しては二重化により冗長性が確保されている。
JR209系 千葉〜佐倉.m4a
総武本線の運用を録音。
〜JR209系について〜
千葉支社管内で運用されていた113系・211系置き換え用に導入された車両で、10両編成を組成していた0番台を4両編成または6両編成に組成変更されたものである。帯色は同支社管内の211系に準じた黄色と青色の房総色である。
ドアエンジン方式の差異から、空気式ドアエンジン装備車(種車が0番台1・2次車)は2000番台、電気式ドアエンジン装備車(種車が0番台3次車以降)は2100番台に区分されている。
6両編成の車両については、元々の10両編成からサハ4両が単純に取り除かれたものであるが、4両編成については他の編成の先頭車と電動車(中間車)から再組成したものも存在する。そのため、4両編成の先頭車の一部には2000番台の空気式ドアエンジン車両と川崎重工業製車両(空気式・電気式の両方)が含まれる。なお川崎重工業製の中間車は車体構造の都合で転用対象外となっている。
車体
外観では行先表示器のLED化、排障器(スカート)を強化型へ交換、併結運転のため、全ての先頭車に電気連結器と自動解結装置が搭載されている。また、2000番台の先頭車には蓄電池と整流装置 (ARf) が搭載されていなかったため、廃車となったモハ208形から流用。
車内は先頭車両の客用ドア間の座席をセミクロスシートへ改造、「ドア3/4閉スイッチ」の設置、2号車に組成されるモハ208形への車椅子対応の大形トイレ(真空式)設置も行われ、設置に伴い窓が埋められ、床下には汚物処理装置も搭載された。
車内非常通報装置は警報式から乗務員と相互に通話が可能な通話式へと変更。
制御装置など
主要機器は転用改造に合わせてE217系と同じ機器への更新工事を実施している。更新内容としてはVVVFインバータ装置と補助電源装置(静止形インバータ)は、制御素子としてGTOサイリスタを用いたものからIGBTを用いた SC88A および SC92 に、制御伝送装置は MON19 に変更。さらに、ブレーキ制御装置や戸閉制御装置など主要機器についても更新され、ATS-P装置や補助電源装置に関しては二重化により冗長性が確保されている。 伊豆箱根鉄道3000系(ステンレス車)三島広小路〜修善寺.m4a
伊豆箱根鉄道駿豆線のステンレス車。乗車時はラブライブのラッピングを車体全体に施していました。
〜伊豆箱根鉄道3000系(ステンレス車)〜
3000系のうち、1000系置き換え用として1987年に登場した第5編成は、従来の普通鋼製車体から国鉄211系電車に準じた軽量ステンレス製に変更。前面デザインは大雄山線用5000系と同一とされ、側面は戸袋窓の寸法も変更され側窓は1段下降式となり、座席配置も車端部のロングシートの定員も変更され、211系に近い印象となりました。
車体配色は、ステンレス次に青帯。
制御装置など
駆動方法はこれまで吊掛駆動のみの車両であった同社で初めて中空軸平行カルダン駆動方式を採用。主電動機は日立製作所HS-836-Krb型で出力は120kW(端子電圧375V時)、歯車比は86:15=1:5.73である。
制御装置は1000系で実績のあった三菱電機製のABFM-168-15MDH系電動カム軸抵抗制御式多段型制御装置を採用した。
制動装置は日本エヤーブレーキ(現:ナブテスコ)製のHRD1-D型電空併用電気指令式電磁直通ブレーキを搭載した。
補助電源装置はステンレス車では機器の軽量・メンテナンスフリー化を考慮して一次形と同能力の静止形インバータ(SIV)に変更し搭載された。また、バッテリーで駆動するバックアップ用の小容量のSIVを搭載して冗長性を高めている。
空気圧縮機は一次型ではHB2000CB形(容量:2000l/min)を搭載しているが、二次型では同容量のHS-20形に変更して、静音性を向上させている。
パンタグラフは中間電動車であるモハ3000形に2基搭載している。第5編成では工進精工所製のKP62AS形菱形パンタグラフを装備したが、最終編成である第6編成では5000系後期車及び7000系との部品共用化を図るため、東洋電機製の下枠交差型パンタグラフのPT48系に変更。
電動車の台車は住友金属工業製のペデスタル式軸コイルバネ型ダイヤフラム式空気ばね台車FS372N形、制御車はFS072N形。これらの台車は親会社である西武鉄道の当時の標準台車であった西武101系や2000系等に採用されたものを同社向けに改良を行い採用。
冷房装置は、三菱電機製の42,000kcal/hの能力を持つ集中式冷房装置CU-72C形を採用。
伊豆箱根鉄道3000系(ステンレス車)三島広小路〜修善寺.m4a
伊豆箱根鉄道駿豆線のステンレス車。乗車時はラブライブのラッピングを車体全体に施していました。
〜伊豆箱根鉄道3000系(ステンレス車)〜
3000系のうち、1000系置き換え用として1987年に登場した第5編成は、従来の普通鋼製車体から国鉄211系電車に準じた軽量ステンレス製に変更。前面デザインは大雄山線用5000系と同一とされ、側面は戸袋窓の寸法も変更され側窓は1段下降式となり、座席配置も車端部のロングシートの定員も変更され、211系に近い印象となりました。
車体配色は、ステンレス次に青帯。
制御装置など
駆動方法はこれまで吊掛駆動のみの車両であった同社で初めて中空軸平行カルダン駆動方式を採用。主電動機は日立製作所HS-836-Krb型で出力は120kW(端子電圧375V時)、歯車比は86:15=1:5.73である。
制御装置は1000系で実績のあった三菱電機製のABFM-168-15MDH系電動カム軸抵抗制御式多段型制御装置を採用した。
制動装置は日本エヤーブレーキ(現:ナブテスコ)製のHRD1-D型電空併用電気指令式電磁直通ブレーキを搭載した。
補助電源装置はステンレス車では機器の軽量・メンテナンスフリー化を考慮して一次形と同能力の静止形インバータ(SIV)に変更し搭載された。また、バッテリーで駆動するバックアップ用の小容量のSIVを搭載して冗長性を高めている。
空気圧縮機は一次型ではHB2000CB形(容量:2000l/min)を搭載しているが、二次型では同容量のHS-20形に変更して、静音性を向上させている。
パンタグラフは中間電動車であるモハ3000形に2基搭載している。第5編成では工進精工所製のKP62AS形菱形パンタグラフを装備したが、最終編成である第6編成では5000系後期車及び7000系との部品共用化を図るため、東洋電機製の下枠交差型パンタグラフのPT48系に変更。
電動車の台車は住友金属工業製のペデスタル式軸コイルバネ型ダイヤフラム式空気ばね台車FS372N形、制御車はFS072N形。これらの台車は親会社である西武鉄道の当時の標準台車であった西武101系や2000系等に採用されたものを同社向けに改良を行い採用。
冷房装置は、三菱電機製の42,000kcal/hの能力を持つ集中式冷房装置CU-72C形を採用。